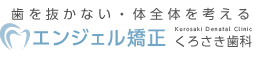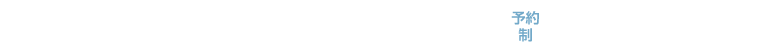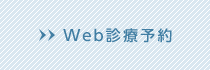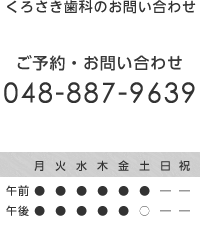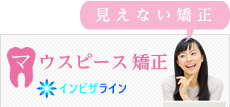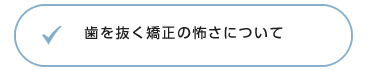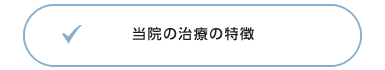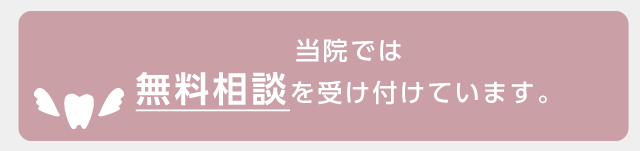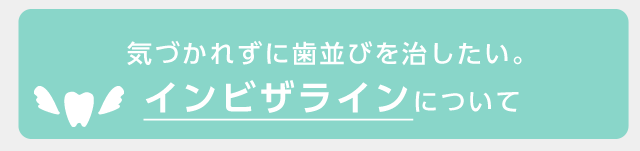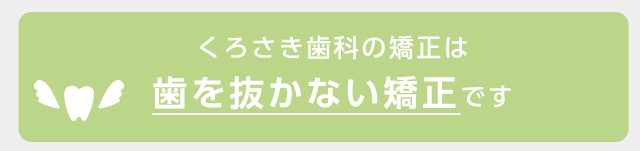歯並びを悪化させる歯周病は糖尿病との相関性がある!?

歯周病は歯並びを悪化させる上に、糖尿病と相関関係があることが明らかになっています。
歯周病のある人は糖尿病になるリスクが上がり、また糖尿病をもっている人は歯周病を発症させやすいことがさまざまな調査で明らかにされているのです。
今回は歯周病と糖尿病との関係についてご説明していきます。
Contents
歯周病で歯並びも悪化する?
歯並びが悪いと歯垢(プラーク)がたまりやすいため歯周病になりやすいのですが、歯周病になると歯並びはさらに悪化します。
細菌の繁殖によって歯茎や歯を支える骨などの歯周組織が破壊され、支えを失った歯が不安定になることで他の歯にも影響を与えるためです。
歯はそれぞれ支え合っているので、歯周病になった歯があると他の歯との間に隙間ができたり、前に押し出されるなどして歯並びを悪化させてしまいます。
このため歯周病の治療と平行しながら矯正治療を行う場合もあります。
歯周病があると糖尿病になりやすい?
糖尿病は血液中の糖分をエネルギーに変えるインスリンというホルモンの働きが低下することで、血液中の糖分濃度が高くなる病気です。
血糖値が高くなると血のめぐりが悪くなりさまざまな合併症を引き起こします。
歯周病で通院している人の中には糖尿病の人が多くいる事実は意外と知られていません。
また糖尿病予備軍の人も多いといわれています。
歯周病があることで糖尿病にかかりやすくなり、また糖尿病があることで歯周病にもかかりやすくなるためです。
歯周病は細菌に感染することで起こる感染症です。
歯周病を引き起こす細菌をやっつけるため免疫細胞が集まってくると、歯周病菌と触れることで「TNF-α」という物質が放出されます。
これは「炎症性サイトカイン」という細胞から出るタンパク質の一種で、この物質が増えて血液中に流れ込むとインスリンの働きが妨げられてしまいます。
インスリンの働きが低下すると血糖値が高くなり糖尿病を進行させてしまいます。
糖尿病が歯周病を悪化させる?
高血糖の状態になると、体外に出される水分量が増え唾液の分泌量が減ってきます。
唾液には口の中を浄化したり組織を修復する働きがあり歯周病菌の繁殖も防いでいます。
口の中が乾いて唾液が十分に分泌されなくなると、このはたらきも弱まり菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。
さらに、血流が悪くなることで免疫機能も低下し細菌がより繁殖しやすくなります。
このようにして歯周の炎症が悪化すると「TNF-α」が分泌されインスリンの働きを妨げる、という負のスパイラルに陥っていくのです。
糖尿病と歯周病の治療を同時に行うと効果的

糖尿病は血糖値が上がることで引き起こされる合併症が怖い病気です。
合併症の例として挙げられる網膜症や腎症が悪化すると失明したり透析が必要になることがあります。
歯周病は糖尿病の第6位の合併症であり、糖尿病も歯周病の2大危険因子とされています。
歯周病を徹底的に治療することによって、糖尿病の血糖値のコントロールが改善できたという報告も増えていて、歯周病と糖尿病を同時にきちんと治療していけば、双方の改善に効果があるといえます。
糖尿病の予防として飲酒や喫煙、間食を控えたり、適度な運動や低カロリー低血糖の食事を心がけることは、同時に歯周病の予防にもなります。
歯周病は自覚症状がなく気付かないうちに進行する病気で、ひどくなると歯並びにも悪影響を与えてしまいます。
早期に発見するためにも定期的に歯科検診を受けましょう。