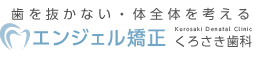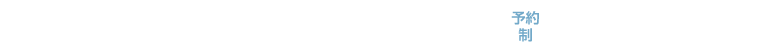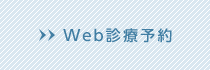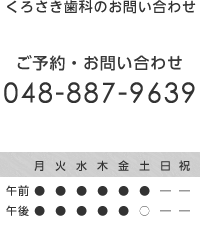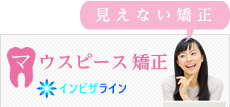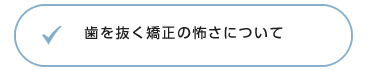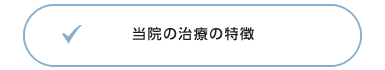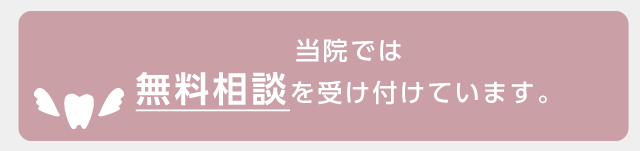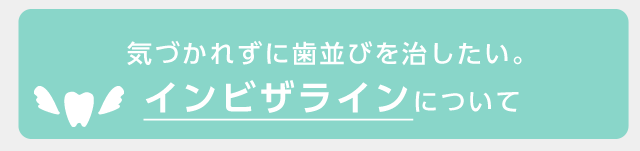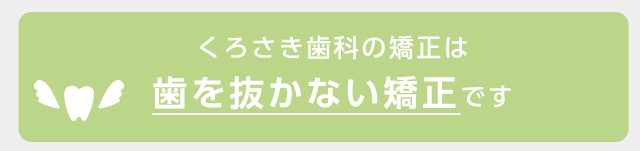睡眠中に起こる歯ぎしりの理由と、その対処法

睡眠中につい奥歯を食いしばってしまう、あるいは、ぎりぎりと歯を噛み合わせてこすり合わせてしまうなどの癖を持つ人は意外に多く、日本人全体の7割にものぼると言われています。
しかし、なぜ望んでもいないのに歯ぎしりをしてしまうのでしょうか。
Contents
歯ぎしりの種類
歯ぎしりには大きく分けて3種類あります。
・グラインディング
上下の歯をすり合わせてぎりぎりと音を鳴らす、歯ぎしりの中でも最も多いタイプです。
歯の磨耗を起こしやすく、歯の付け根が削れたり、知覚過敏になりやすいです。
・クレンチング
上下の歯をぎゅっと強く噛みしめた状態で顎に大きな力がかかっています。
音はしないので周囲には気付かれにくいですが、歯が欠けたり割れてしまう場合があります。
・タッピング
上下の歯をカチカチとぶつける歯ぎしりでまれにみられるタイプです。
歯ぎしりをする理由は?
歯ぎしりの最も大きな理由はストレスと考えられています。
飲酒や喫煙、特定の抗うつ剤で引き起こされるケースもありますが、一種の癖でもあるため根本的な治療が難しいです。
噛み合わせの急激な変化、歯並び、顎や歯の加齢による擦り減りなどを歯ぎしりの理由とする話はよくありますが、科学的根拠は見つかっていません。
やはり最大の理由はストレスだとする説が有力です。
ただし、歯ぎしりをしているとこれらの症状が悪化してしまうため、虫歯や歯の擦り減り、歯並びの悪さは放置せず歯科で治療を受けておいたほうが良いでしょう。
ちなみに子どもが歯ぎしりをする理由は、成長途中で嚙み合わせの変化に対応するためなので、多くの場合は自然に治るとされています。顎などの痛みが引かない場合は小児歯科などで相談しましょう。
歯ぎしりをやめるには?

1.マウスピースを使った治療を受ける。
歯科ではマウスピース(スプリント)を使う治療法が一般的です。
睡眠中にマウスピースを使うことで顎や歯への負担を減らすことができます。
市販のマウスピースでは逆に噛み合わせを悪くしてしまうことがあるので、歯科で合ったものを作ってもらいましょう。
2.首や肩などの筋肉の凝りを解消する。
歯ぎしりをよくやっている人は睡眠中首や肩にぐっと力が入った状態なので、筋肉がつねに緊張しています。
肩や首を意識的に動かしたり温めたりして筋肉を緩めるように心がけましょう。マッサージや整体などでほぐしてもらうのも良いでしょう。
3.普段歯を噛みしめないように意識する。
正常の状態では上下の歯には1~2㎜程度の空間があいています。
歯を噛みしめ上下の歯が接触しているとき、身体が緊張状態になり脳に刺激が送られていると考えられています。
そのため、何かに集中しているときに歯を噛みしめやすい人は睡眠中も歯ぎしりしやすいです。
運転中、パソコンなどでの作業中、テレビや映画を鑑賞中などに歯を噛みしめていないか時々確認してみましょう。
4.ストレスを解消し、寝る前はリラックスする。
運動や好きなことをしてストレスを解消することも大切です。
心配事や悩み事を書き出して気持ちを整理してから寝たり、寝る前はゆったりと入浴して副交感神経を高めたりして、心身に負担をかけない生活を目指してください。
歯ぎしりは歯の損傷だけではなく、歯周病の進行、骨の隆起、偏頭痛などさまざまな症状が現れます。
身体に大きな負担がかかるので放置しないようにしましょう。