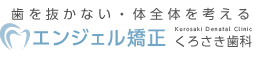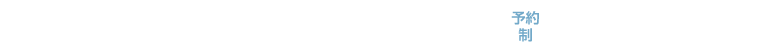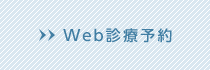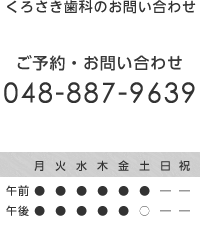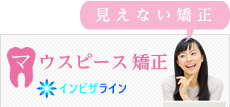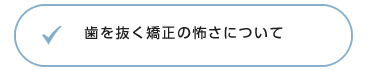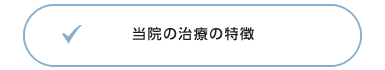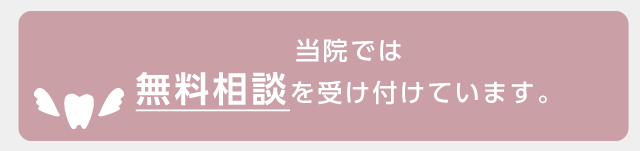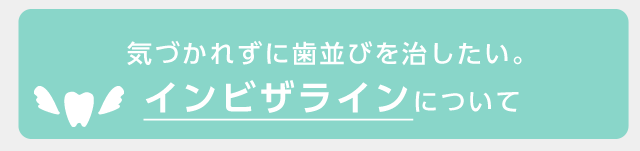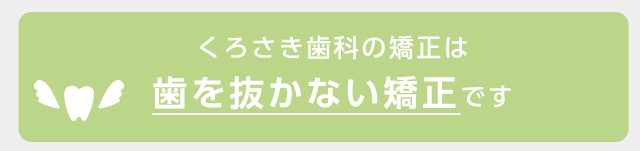肩こりも? 悪い「噛み癖」が身体に与える影響とは

原因不明の頭痛、肩こり、耳鳴りに悩んでいるという方は「噛み癖」にその原因があるかもしれません。
自分では気づかずに歯と歯を噛み合わせていることにより、体のあちこちにさまざまなトラブルが生じると言われています。
今回はこの噛み癖が身体に与える影響について詳しくご説明します。
Contents
無意識に起こる歯列接触癖
まず、テレビを見たり本を読んだりする時、唇を閉じた状態で上の歯と下の歯がどうなっているかをチェックしてみてください。
本来は唇が閉じていても上下の歯は離れているのが正常な状態です。
上下の歯を噛みしめてしまう方は「歯列接触癖」があるということになります。
歯列接触癖の原因
歯列接触癖の原因はさまざまなものがあります。
・虫歯や歯周病
虫歯や歯周病で歯並びが変化し、噛み締めやすい歯並びになることが原因となるケース。
・精神的ストレス
緊張したり大きなストレスを感じたりすることで歯を食いしばるようになるケース。
・作業に集中するとき
精密作業やパソコン業務などで集中すると歯を噛み合わせてしまうケース。
人間は緊張したり力を入れるときに歯を食いしばるものですが、その状態が常に続いてしまうのがこの癖の特徴です。
歯列接触癖が体に及ぼす影響

・頭痛や体のコリ
「頭痛持ちである」「いつも首や肩が凝っている」「耳鳴りやめまいが頻繁に起こる」などといった人は、歯列接触癖によって体の筋肉を常に緊張させ、筋肉疲労を起こして体のあちこちに痛みや凝りを感じている可能性があります。
・ガスが溜まりやすい
歯を噛み合わせていると常に唾液が出てくるので、唾液を飲みこむ回数が増えて同時に空気もたくさん飲み込んでしまいます。
飲み込んだ空気がガスとなりお腹に溜まっておならやゲップが出やすくなります。
・顎関節症
噛み癖は顎関節にも過度な緊張を与え、関節の血の巡りを悪くさせます。
これによって徐々に顎関節が変化してずれが生じると痛みが出てしまい、顎関節症が進行していきます。
・歯周病や口内炎
噛み癖によって歯茎や歯の根元に強い力が加わり続けると、歯周囲組織が破壊されて歯周病が進行してしまいます。
また、奥歯で噛み合せた時に頬粘膜を傷つけてしまい、口内炎が慢性化する場合があります
歯列接触癖の改善方法
・意識して噛み癖をやめる
ふとした時に意識して歯を離したり、家具や壁などに「噛み癖を治す」などの張り紙を貼って自分自身に気づかせるよう配慮してみましょう。
・呼吸を意識する
歯と歯を噛み合せたままで息を吐くことは難しいため、気づいたら呼吸を意識して息を吐く時に少し口を開け、歯と歯を離すように意識しましょう。
・歯科医師に相談する
歯科で治療する方法もあります。歯を削って噛み合わせを調整する、マウスピースで食いしばりを抑制する、噛み癖の原因となる虫歯を治療する、矯正で歯並びを整えて噛み癖を軽減するなどさまざまな治療を施してくれます。
歯科医師の診察により、自分ではわからない原因を見つけることもできます。
自分ではなかなか改善できない噛み癖は専門家である歯科医師に相談するのが一番と言えるでしょう。
噛み癖は体の凝りを悪化させるだけでなく、歯周病や歯並びにも大きな影響を与えます。
噛み癖に気づいたら、できるだけ早く対処することでさまざまなトラブルを回避し歯を健康に保つことができます。
噛み癖が原因で体に不調が起きていた場合は、少しずつ意識して改善していくことで体調も徐々に良くなっていくはずですよ。