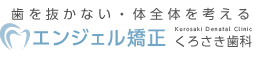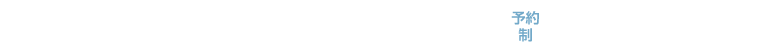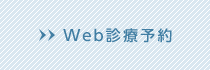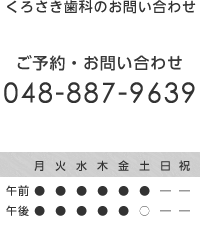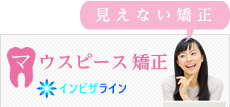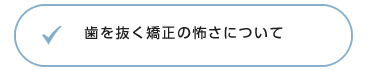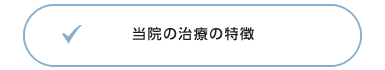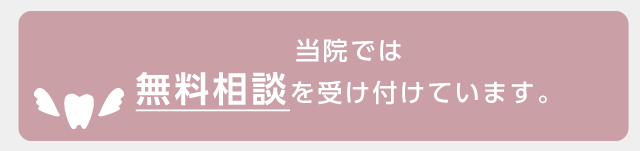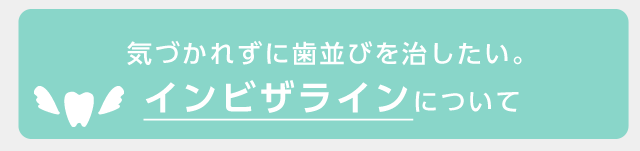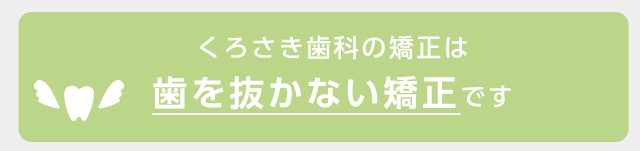遺伝?習慣?子どもの歯並びに悪影響を与えるものとは

歯並びは生活やコミュニケーション、あるいは性格にまでも影響を与えます。
できることであれば、子どもにはキレイな歯並びをした大人に育ってほしいものですよね。
しかし、歯並びは「遺伝」するという説がささやかれており、落胆しているご両親も多いようです。
はたして、本当に歯並びは遺伝するのでしょうか?
Contents
歯並びに遺伝は関与する
子どもの顔つきが親に似るように、骨格も継承されます。
それは歯が並ぶあごの骨も例外ではありません。
歯並びが直接遺伝するというわけではありませんが、骨格が似ると歯並びも似たような配列になりやすいのは確かで、親の歯並びがガタガタだと、子どもの歯もガタガタになりやすくなります。
ただし、歯並びが悪くなる原因は先天的なものよりも後天的なものが大きく、遺伝以上に子ども自身の生活習慣のほうが歯並びに影響を与えやすいです。
遺伝のことを心配するより、悪習慣を繰り返していないかチェックしてあげるよう心がけてください。
歯並びに悪影響を与える習慣とは

≪食事方法≫
食事中はあごと歯を使うため、食事方法が適切でないと歯列不正の原因となります。
たとえば噛む回数が少ないと、あごが十分に発達せず、歯が綺麗に並ぶことができません。
前歯を使わない食事を続けたり、食事中の姿勢が悪くても歯並びに悪影響を与えてしまいます。
お子さんの食事には前歯も使うような噛みごたえのあるものを用意し、正しい姿勢を教えてあげましょう。
また、柔らかいもの・甘いものばかりを食べているのも危険です。
おのずと噛む回数が減りますし、虫歯にもなりやすくなります。
特に清涼飲料水は摂り過ぎると歯のエナメル質を溶かしてしまうので、摂取量をコントロールしてあげましょう。
≪生活上での癖≫
誰しも癖のひとつやふたつはあるものです。
しかし一見かわいらしく見えるお子さんの癖が、歯並びに悪影響を与えている恐れがあります。
その代表的なものが「頬杖」です。
頬杖を繰り返していると片方だけに圧力がかかり、歯並びをゆがませてしまいます。
その他、いつも横向きで寝ている、おしゃぶりをする癖が抜けないなどの場合も心配です。
できるだけ優しく注意をして、改善を促してあげましょう。
≪口周りや口内の影響≫
お子さんはテレビを見ている時に、ポカンと口を開けていませんか?
開いてしまっている場合、口呼吸をしている恐れがあります。
口呼吸を続けていると上あごの成長が進まず、出っ歯や不揃いの原因となってしまうでしょう。
鼻づまりや他の疾患がないか、チェックしてあげることが大切です。
また、歯の欠損や虫歯を放置していると歯並びが悪くなります。
歯科医院での定期検診を受けて、お子さんの大切な歯を守っていきましょう。