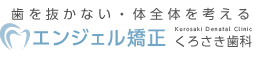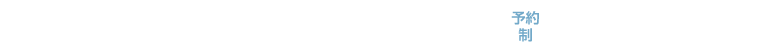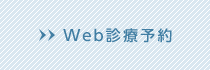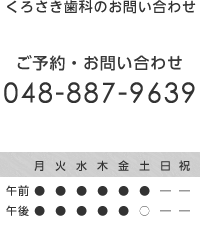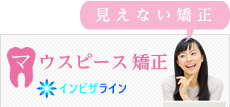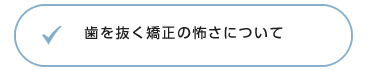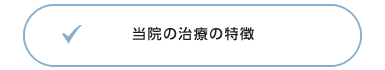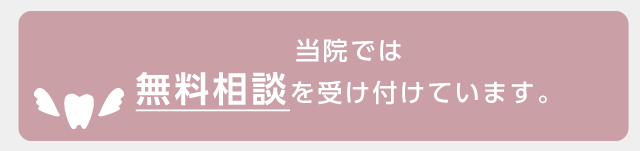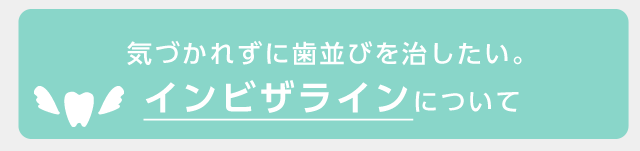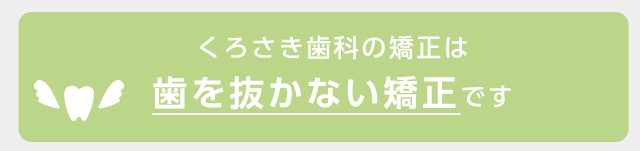歯ぎしりが歯並びと健康に与えるリスクを知ろう

歯ぎしりはなかなか自分では気づけません。
でも、人と一緒に寝たときに「歯ぎしりしていたよ」なんて言われたことがある人もいるでしょう。
歯ぎしりやいびき、寝言などは「恥ずかしい!」で済ませてしまっているかもしれませんが、実は身体に悪影響を及ぼしていることもあるのです。
なぜ歯ぎしりをしてしまうのか原因を知っておくと、改善方法が見えてくるでしょう。
Contents
歯ぎしりには種類がある!
歯ぎしりは、睡眠医学で「ブラキシズム」という病気としてとらえられています。
このブラキシズムには種類があります。
一つ目は上下の歯をギリギリとこすり合わせる「グラインディング」というタイプで、もっとも一般的な歯ぎしり。
二つ目は無意識のうちに奥歯を強く噛みしめる「クレンチング」というタイプで、睡眠時だけでなく起きている時もしていることがあります。
三つ目は「タッピング」といって、上下の歯をカチカチと噛みあわせるタイプ。タッピングはあまり身体に影響を及ぼすことはありませんが、ブラキシズムの兆候として意識しておいた方がいいでしょう。
歯ぎしりの原因は?

歯ぎしりの原因となるのは主にストレスだと言われています。
日中ため込んだストレスをうまく発散できないまま眠りにつくと、ぐっと奥歯を噛みしめてしまうのです。
それから、歯の治療中も歯ぎしりを起こしやすいです。
詰め物をした歯の高さが合っていなくて咬みあわせが悪かったり、抜いた歯がそのままになっていて顎の筋肉のバランスが崩れていると歯ぎしりをしてしまいます。
歯並びが悪くて咬みあわせがずれているのもよくないですね。
逆流性食道炎の症状がある人も歯ぎしりをしやすいと言われています。
歯ぎしりが続くと身体に悪影響を及ぼす

歯ぎしりをしているときは、歯に70kg以上の力がかかっています。
歯ぎしりを長期間していると大きな負担がかかり続けることになりますので、歯がかけたり、折れたり、歯のエナメル質が壊れて知覚過敏になってしまう可能性があります。
また、強い力で噛みしめることで顎の疲れがとれなくなるという影響も。
さらに悪化すると顎関節症になってしまうことも考えられます。
顎関節症になってしまうと口が開かなくなったり、肩こりが深刻化するなどさらに問題は増えていきます。
また、長期間噛みしめていると顎の筋肉が発達し、エラが張ってくるのでフェイスラインが変わってしまう恐れもあります。
そしてこれはあまり知られていませんが、歯ぎしりは歯周病を悪化させる原因にもなります。
もし人に「歯ぎしりしていたよ」と注意されたら、疲れているのだろうなどと放っておかず、ストレス発散をしたり歯の治療をして改善するようにしたほうがいいでしょう。