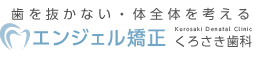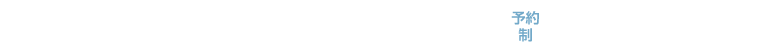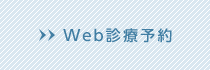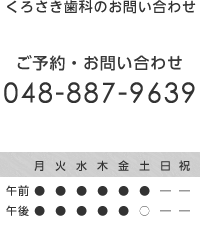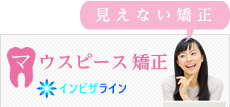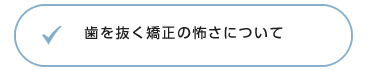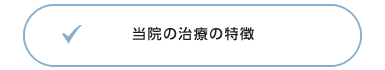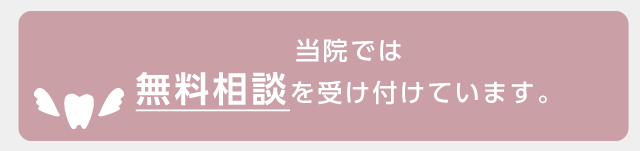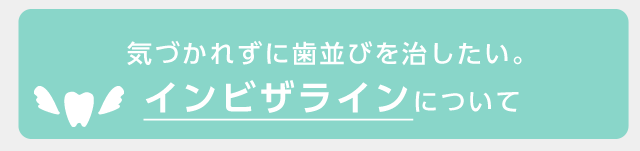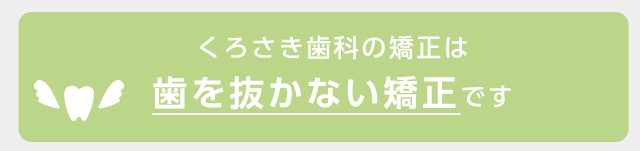不正咬合の種類とそれぞれの原因や治療法

整っていない歯並び(不正咬合)は見た目の問題だけではなく、生活のしにくさや体調不良の原因にもなるものです。
不正咬合にお悩みの方はできるだけ早めに歯科医に診てもらうようにしましょう。
不正咬合にはいくつか種類があり、それぞれで原因や治療法などが異なります。
不正咬合の種類を知っておき、正しい対処ができるようにしておくことも大切です。
ここでは、不正咬合を種類別に紹介し、それぞれの原因や治療法などをご紹介します。

Contents
叢生(そうせい)
日本人の不正咬合の中でも発生率が最も高いと言われているのが「叢生(そうせい)」です。
叢生とは、歯が顎の中に納まりきらずデコボコと重なりあうようにして生えている状態のことを言います。
叢生という言葉を聞いたことのある人は少ないかもしれません。
しかし八重歯も叢生の一種とされるなど、叢生の状態になっている方は実際に多いのです。
叢生になると、歯磨きをまんべんなく行いにくくなるため、虫歯や歯周病などにかかりやすくなると言われています。
【叢生の原因】
叢生は顎が小さいことを原因として起こります。
顎が小さいと、永久歯が生えるための場所がなく、後から生えてきた歯は歯列からはみ出さざるを得なくなります。
その結果、歯が横や前に飛び出し、歯並びの悪い状態になってしまうのです。
顎の大きさは食生活と深い関わりがあるとされており、幼い頃に柔らかいものばかり食べていたり、よく噛まずに飲み込んだりしていることで、顎の発達が抑えられてしまいます。
子育て中の方は、お子様がよく噛んで食べているかどうかしっかり注意してあげるようにしましょう。
【叢生の治療法】
叢生は基本的に矯正により治療をします。
顎が未発達の子どもであれば、非抜歯で行うことも可能です。
顎が発達し、永久歯も生えそろった大人の場合は、抜歯が必要になることもありますが、矯正による治療ができます。
また、軽度の叢生であれば歯を削るだけで改善することも可能ですので、歯科医師に相談してみましょう。

上顎前突(じょうがくぜんとつ)
上顎前突(じょうがくぜんとつ)は叢生に続いて、日本人がなりやすい不正咬合になります。
いわゆる「出っ歯」のことです。
上顎前突は、上の歯が下の歯よりも前方に出っ張っている状態のことです。
上の歯に傾斜ができて飛び出しているケースと、下顎が上顎よりも小さく、上顎の歯茎自体が前方に飛び出しているケースとに分けられます。
上顎前突になると、唇が閉じにくくなり口呼吸が習慣化しやすくなってドライマウスになりやすくなります。
ドライマウスは唾液の分泌量を減らし虫歯や歯周病を引き起こすので注意が必要です。
また、飛び出した前歯が唇に触れて皮膚を傷つけたり、スポーツをしている際などに折れやすくなったりします。
ほかにも下顎をずらして噛む癖がついて顎の関節に負担がかかりやすくもなるなど、上顎前突にはたくさんのリスクがありますのでできるだけ早めに治療をしましょう。
【上顎前突の原因】
上の歯に傾斜ができることで発生する上顎前突(歯性の上顎前突)は、幼少期の指しゃぶりが原因になると言われています。
指しゃぶりをすると、舌で前歯を押すことになります。継続的に前歯に力をかけることによって歯に傾斜ができてしまうのです。
また口呼吸を習慣的に行うことによって唇の筋肉が緩み、歯に傾斜ができてしまうとも言われています。
下顎が上顎よりも小さいケースの上顎前突(骨格性の上顎前突)は親からの遺伝が主な原因であるとされています。
【上顎前突の治療法】
歯性の上顎前突は、ワイヤー矯正や裏側矯正などによって前歯を正しい位置に戻すことで治療を行います。
歯の生え方を矯正するものですので、部分矯正などで改善することも可能です。
骨格性の上顎前突は上顎全体を矯正する必要があります。
歯を移動させなくてはならなくなるため奥歯を抜歯することもありますので、治療前にしっかり歯科医師と相談するようにしましょう。

空隙歯列(くうげきしれつ)
空隙歯列(くうげきしれつ)とは、いわゆる「すきっ歯」のことです。
上顎前突と同じくらいの数の患者がおり、日本でよく見られる不正咬合のひとつになります。
歯と歯の隙間に空間ができることで、見た目のコンプレックスにもなりますし、発声の際に空気が隙間から漏れ出て、聞き取りにくい発音になってしまう原因にもなるとも言われています。
また隙間に食べかすが溜まりやすく、虫歯や歯周病の発症リスクも高まりますので注意が必要です。
【空隙歯列の原因】
空隙歯列は顎の大きさと歯の大きさに差が生じることで発生します。
通常よりも歯のサイズが小さかったり、通常よりも顎が大きかったりすることで歯と歯の間に隙間ができてしまうのです。
先天的に永久歯の数が少ない、もしくは上唇小帯に付着異常がある、埋伏歯があるなどの場合にも空隙歯列になることがあります。
また、虫歯や歯周病が原因で奥歯を失ってしまった結果、前歯に隙間ができてしまうケースもあります。
【空隙歯列の治療法】
全体的に隙間が見受けられる場合は、矯正によって歯を動かし治療します。
ワイヤー矯正やインビザラインなどのマウスピース矯正も行うことができるので、歯科医師と相談して行いましょう。
前歯のみに隙間がある場合は、ラミネートべニアやオールセラミックといった被せ物によって症状を改善することができます。
ラミネートべニアは歯の表面を削ってそこに薄いセラミックを接着する治療法で、オールセラミッククラウンはセラミックの被せ物を装着する施術です。
基本的に着色改善のために用いられるものですが、空隙歯列の改善にも効果があるとされています。

開咬(かいこう)
開咬(かいこう)とは口を閉じたときに、奥歯が噛み合っているのにもかかわらず前歯が噛み合っていない状態のことを言います。
「オープンバイト」とも呼ばれ、常に上下の前歯が開いてしまっている状態です。
それほど多く見られる不正咬合ではありませんが、食べ物を上手く噛むことができなくなり胃腸への負担が大きくなって胃腸障害などにつながる恐れがあるので注意しなくてはいけません。
また、上下の前歯が噛み合わないことによって息が漏れ出てしまい、発音の問題なども発生しやすくなります。
ほかにもドライマウスになりやすくなる、奥歯ばかりで噛むようになって顎に負担がかかり顎関節症になるなど、いろいろなトラブルの原因にもなるので早めに歯科医に診てもらうようにしてください。
【開咬の原因】
開咬の原因には先天的なものと後天的なものとがあります。
後天的な開咬の原因には以下のようなものがあります。
・口呼吸の習慣化
鼻炎や蓄膿症、アデノイド肥大など、成長期に呼吸器系の疾患が多くなると口呼吸が習慣化しやすくなります。
口呼吸を続けることで唇の筋肉が弱くなり、口腔内のバランスが崩れて開咬になりやすくなります。
・指しゃぶり
幼少期に指しゃぶりを頻繁にすることで、前歯に過度な力が加わってしまい開咬になりやすくなります。
【開咬の治療法】
子どもであれば開咬の原因になる習慣を直しながら矯正治療を行うことで治療をします。
抜歯せずに治療も可能なので、お子様に開咬の疑いがある場合はできるだけ早めに治療をするようにしてください。
大人が開咬の治療をする場合はワイヤー矯正やインビザラインなどマウスピース矯正を行います。
顎が小さいなどの場合は奥歯を抜いて歯を移動させるスペースを作るケースがあります。
治療前にはしっかり歯科医師と相談するようにしましょう。

過蓋咬合(かがいこうごう)
上下の前歯の噛み合わせが深くなり、上の前歯が下の前歯を覆ってしまう状態のことを過蓋咬合(かがいこうごう)と言います。
通常、前歯は噛み合わせたときに、上の歯が下の歯を2、3ミリ覆っているものです。しかし過蓋咬合になると下の前歯がほとんど見えなくなるくらいまで上の歯がかぶさってしまいます。
上の歯が下の歯を覆ってしまうことで、下顎が極端に動かしにくくなります。
その結果顎への負担が大きくなって口を開けにくくなったり、口を開けるたびにガクガクと音が鳴ったりなど、顎関節症を引き起こす可能性があるので注意が必要です
ほかにも歯が接触することで歯がすり減る、歯茎に傷がつきやすくなる、咀嚼がしにくくなる、発音が悪くなるなど、さまざまなお口トラブルの原因にもなるので、できるだけ早めに歯科医に診てもらうようにしてください。
【過蓋咬合の原因】
過蓋咬合にも、遺伝による骨格や歯並びの異常などを原因とするものと、後天的な原因によるものとがあります。
後天的な原因には、虫歯などで奥歯を抜いたままにしておくことで噛み合わせが悪くなることが挙げられます。
ほかにも、強く噛みしめすぎる、下唇を噛んだり吸ったりするクセがある、頬杖をつくクセがあるなども過蓋咬合の原因になりますので注意しましょう。
【過蓋咬合の治療法】
顎の成長が進んでいない子どもであれば、噛み合わせを整えてあげることで過蓋咬合の予防や改善につなげることができます。
顎が成長しきった大人であれば、矯正器具で奥歯を引っ張ることで高さを増し、前歯を歯茎のほうへ入り込ませるよう移動させることで噛み合わせを浅くします。
過蓋咬合も年齢が若ければ若いほど簡単な施術で治療できますので、できるだけ早めに歯科医に診てもらうようにしてください。

下顎前突(かがくぜんとつ)
「受け口」と呼ばれることが多い下顎前突は、下の歯が上の歯よりも前に出てしまい、噛み合わせが通常のものと逆になっている状態のことです。
見た目的にも悪くなるのと同時に、噛んだり話をしたりがしにくくなるなどのトラブルにつながります。
下顎前突には、下の顎が上の顎よりも大きくなることで起こる骨格性のものと、上の歯が後ろに傾斜したり下の歯が前に傾斜したりすることで起こる歯性のものとがあります。
顎関節症の原因になったり、発音が不明瞭になったりするなどたくさんの問題の元になりますので、できるだけ早い段階での治療が好ましいです。
【下顎前突の原因】
下顎前突は遺伝によって起こることがほとんどであると言われています。
ただ、すべてが先天的なものではなく、幼いときの指しゃぶりの癖や、舌で下の歯を押す癖、下顎を前に出す癖、頬杖をつく癖など、後天的な要因によって起こることもありますので注意しましょう。
【下顎前突の治療法】
子どもの場合は、ムーシールドと呼ばれる取り外しが可能な矯正器具を使い顎の成長をコントロールしながら改善していきます。
大人になると、歯列全体を矯正することになります。唇側矯正や裏側矯正など一般的な矯正や、インビザラインなどマウスピース矯正を行うことになりますので、事前に歯科医師と相談しましょう。
子どものほうがより簡単な方法で改善できるので、可能な限り早いうちから治療を始めるようにしてください。

不正咬合の種類と、それぞれの原因や治療法をご紹介しました。
ここで紹介した通り、不正咬合は基本的に顎や歯が成長しきる前に治療することでよりスムーズな改善が可能になります。
自分や家族が不正咬合なのではないかと思われる場合は、できるだけ早く歯科医に診てもらい、適切な処置を施してもらうようにしてください。