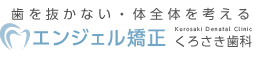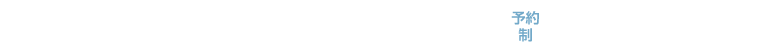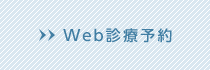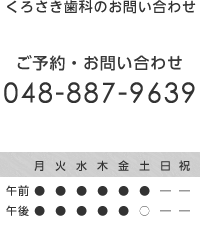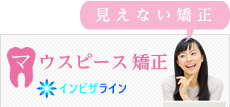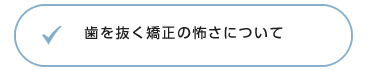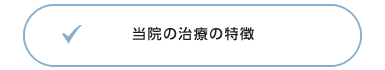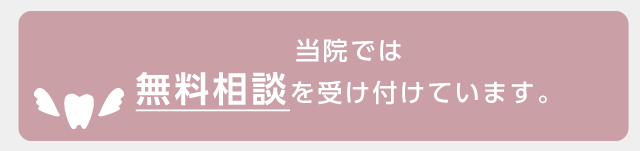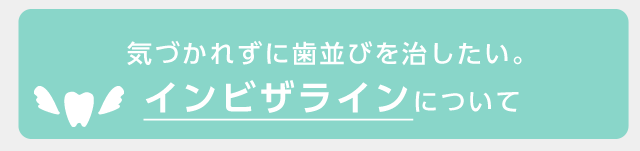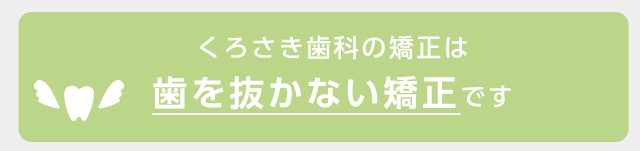どうして歯茎が腫れる? 歯茎の腫れの原因と対処法

口の中に違和感を覚えて見てみると、どういうわけか歯茎が腫れていた、という経験があるという方も多いのではないでしょうか。痛みが伴うこともあるかもしれませんが、場合によっては痛みもないのに歯茎だけが腫れているということもあると思います。
歯茎が腫れているだけでも口の中に異物感があり、落ち着かないですよね。原因を探って、早急に対処したいものだと思います。
どうして歯茎は腫れてしまうのでしょうか。ここでは、歯茎が腫れてしまう主な原因と対処法などをご紹介します。

Contents
歯茎が腫れる原因① 歯周病
歯茎が腫れる原因として考えられる最も有力なものが、歯周病です。歯肉炎、歯周炎など、症状の度合いによって呼び方が変わりますが、歯茎に炎症が起こり、歯茎や歯を支える骨(歯周骨)が溶かされてしまうという点では変わりません。歯茎の炎症にとどまっているものが歯肉炎、歯周骨まで症状が進んでいるものが歯周炎と呼ばれます。
歯周病は日本人が歯を失う最大の要因であると言われていますが、自覚症状が出ないことが多く、気が付いたら深刻な段階まで病気が進んでいるということがありますので注意が必要です。
「痛みはさほどないけど、ちょっと歯茎が腫れているような感じがする」というように、歯茎に少しでも違和感がある場合は、歯周病を疑いましょう。
【歯周病による歯茎の腫れの特徴】
歯周病が原因である場合、一般的に歯磨きがしにくい奥歯や歯と歯茎の間あたりを中心に腫れが生じます(歯周病が、歯周ポケットにたまった歯垢が原因で発症するからです)。噛んだときにちょっと痛む、しみる、などを感じる場合は、すぐに歯科医師に診てもらいましょう。

歯茎が腫れる原因② 親知らず
歯茎が腫れる原因のひとつに、親知らずが変な向きで生えようとしているというものがあります。歯茎の中に埋もれている親知らずが、横向き、斜め方向など、変な方向に生えようとすることで、歯茎に負担がかかって腫れてしまうのです。
また、親知らずが変な方向に生えた場合、歯と歯茎の間に歯ブラシの届きにくい隙間ができてしまいます。そこに歯垢がたまって炎症が起こり、歯茎の腫れにつながることもあります。
【親知らずによる歯茎の腫れの特徴】
痛みが伴う場合があり、寝不足、疲労による免疫力が低下しているときなどに腫れが出やすくなる傾向があります。放置しておくと腫れが大きくなり、頬も腫れてしまうことも。場合によっては喉が痛むこともあります。

歯茎が腫れる原因③ 虫歯
虫歯になると歯茎が腫れることが多いです。虫歯の場合は激しい痛みを伴うなど、腫れ以外の自覚症状が出ることがほとんどですし、歯茎が風船のように大きく腫れあがる(膿を伴うため)など、特徴が顕著ですので、口の中の異変に気が付かないということはめったにないと思います。しかし放っておくと口内環境を悪化してしまいますので、違和感に気付いたらすぐに歯科医師に診てもらうようにしてください。
【虫歯による歯茎の腫れの特徴】
歯茎に膿がたまることで腫れが生じます。その膿が神経を圧迫することで、激しい痛みを伴うというのと、風船のように膨らむというのが主な特徴です。それらの自覚症状があるような場合は、すぐに歯医者へ行き、神経を取り除くなどの虫歯治療を受けるようにしましょう。

歯茎が腫れる原因④ 口内炎
栄養不足やストレス、心身の疲れなどがもとで生じる口内炎が、歯茎の腫れの原因であることもあります。一か所にだけできるという場合には、歯茎の腫れというよりも「口内炎ができた」と感じるだけだと思いますが、同時に複数個できるなどで腫れが大きくなり、まるで歯茎が腫れているように感じられることもあるかもしれません。
【口内炎による歯茎の腫れの特徴】
口内炎の場合、患部に白い潰瘍ができます。刺激の強いものを食べるときなどに、しみたり痛みを感じたりすることがあるでしょう。栄養バランスのとれた食事を心がけ、心身の疲れをとるなどに気を付けていれば、自然と治ります。ただし、同時に複数個できた場合は、別の病気が原因になっていることも考えられますので、すぐに歯医者などの専門機関で診療してもらうようにしてください。
歯茎が腫れるその他の原因
歯茎が腫れる原因として考えられる主な原因を紹介しましたが、歯茎の腫れの原因になりえるものは、ほかにもいくつかあります。
・アルコールの過剰摂取
アルコールを過剰摂取すると、アルコールの分解に体力が費やされ、体の免疫力低下につながります。免疫力が低下することで細菌が繁殖し、歯茎の腫れにつながることがありますので、アルコールの過剰摂取は極力控えましょう。
・強すぎる歯磨き
歯磨きする力が強すぎることで、歯茎の腫れにつながることがあります。歯磨きはできるだけ優しく行うようにしましょう。
・骨髄炎やガン
骨に細菌が感染し炎症を起こす骨髄炎によって歯茎が腫れることがあります。また、ガンなどの腫瘍が原因になっていることもあります。大きな病気が原因になっていることもありますので、歯茎が腫れたらすぐに歯科医師に診てもらうようにしてください。
・根尖病巣(こんせんびょうそう)
膿を伴った歯茎の腫れです。歯根膜炎と呼ばれることもあります。痛みを感じる頻度は低いですが、突然急激な痛みを感じることがあります。口内環境を悪化させるものですので、早めに治療をしてもらうようにしましょう。
・薬の副作用
高血圧や心臓病の薬を飲んでいる場合、その薬の副作用として歯茎が腫れることがあります。
・残っている歯の破片
抜歯治療などを受けると、歯の根の破片が歯茎の中に残ってしまうことがあります。普通は自然となくなるものですが、まれに消えないことがあり、歯茎の腫れにつながってしまうことがあるのです。

歯茎が腫れているときの対処法
ここまで紹介した通り、歯茎が腫れているのは歯周病や虫歯、場合によっては腫瘍や骨髄炎などのような重大な病気が原因になっていることがあります。歯茎が腫れている場合は、できるだけ歯科医師に診てもらうことをおすすめしますが、時間帯や個人の事情によっては、すぐに歯医者へ行けないこともあるでしょう。
そのような場合には、とりあえず自分でできる応急処置を施すようにしてください。歯茎が腫れたときに自分でできる対処法をご紹介します。
・冷やす
歯茎の腫れやそれに伴う痛みは炎症によるものがほとんどです。濡れタオルやタオルに包んだアイスノンなどで、腫れている部分を外側から冷やして、炎症を抑えましょう。鈍痛などが緩和しやすくなります。
ただし、気を付けなくてはならないのが、冷やし過ぎてはいけないということ。冷やし過ぎると血流が悪くなり、腫れの治りが遅くなります。
・痛み止めを飲む
腫れと共に激しい痛みがあるようなら、市販されている痛み止め薬を飲みましょう。一時的ではあるものの、痛みを抑えてくれます。痛みがあると、飲んだり食べたりがしづらくなり、必要な栄養補給が行えなくなってしまうことがあります。痛みが激しい場合は、躊躇せずに痛み止めを飲みましょう。ただし、頻繁に飲みすぎると効果が弱くなってしまいますので、やはり、痛みが激しいときは早めに歯科医師に診てもらうようにしてください。
・歯磨きやうがいをする
歯茎の腫れや痛みは細菌が原因で起こるものがほとんどですので、口の中を清潔にするようにしましょう。うがいをする際は、殺菌効果のあるうがい薬を使うといいでしょう。歯磨きは、できるだけ柔らかいものを使い、奥歯と歯茎の隙間をマッサージするように行います。口の中の細菌が減ることで、腫れや痛みが緩和することがありますので、参考にしてみてください。
・安静にする
疲労により体の抵抗力が落ちることで、歯茎が腫れてしまうことがあります。抵抗力が落ちると細菌が繁殖しやすくなりますので、歯茎が腫れた場合はゆっくりと安静して、体力が回復するように心がけてください。

歯茎の腫れを予防しよう
別の病気などが原因ではない限り、歯茎の腫れの原因のほとんど歯茎と歯の隙間にたまった歯垢によるものです。
日頃からデンタルケアを心がけることで、歯茎の腫れを未然に防ぐことができます。歯茎の腫れの予防をいくつかご紹介しましょう。
・歯周病、虫歯対策になっている歯磨き粉を使う
歯磨き粉は、口臭予防、ホワイトニング、虫歯予防など、さまざまな効用を持ったものが販売されています。歯茎の腫れ予防に適しているのは、歯周病予防効果や虫歯予防効果があるものです。
・歯ブラシはヘッドが小さいものを
歯茎の腫れ予防には、歯を1本1本しっかり磨くことが大切になります。そのため、歯ブラシはヘッドが小さいもののほうがベター。小さなヘッドで、1本ずつ磨くような気持ちで歯磨きしてみてください。
歯ブラシは、ヘッドの大きさに加えて、毛先の柔らかいものがおすすめです。また、電動歯ブラシであれば効果的に磨くことができるので、試してみる価値があるでしょう。
・食後のうがいを習慣づける
口の中に細菌がたまってしまわないようにするのが、何よりも肝心です。外出先から帰ったら手洗いうがいをするように、食後にもうがいを行い、口の中に細菌がたまってしまわないようにしましょう。
もちろん、食後の歯磨きも大切です。できるだけ優しく、力強く磨きすぎないようにして行うようにしてください。

歯茎の腫れは口内環境が悪化していることや、体のどこかに異変が起こっていることを伝えるサインのようなものです。病気にかかっている可能性もありますし、疲れがたまりすぎているのかもしれません。
歯茎が腫れていることに気付いたら、すぐに歯科医師に診てもらうようにすることが重要です。すぐに診てもらえないというような状況であれば、ここで紹介した対処法を試してください。
普段からデンタルケアをしっかり行い、整った口内環境を目指しましょう。