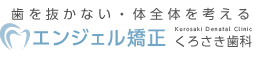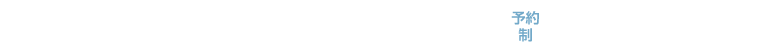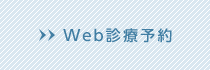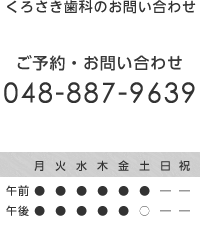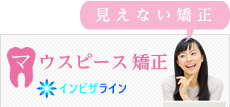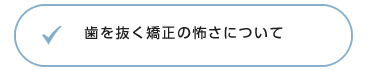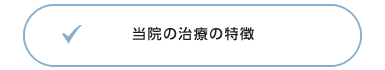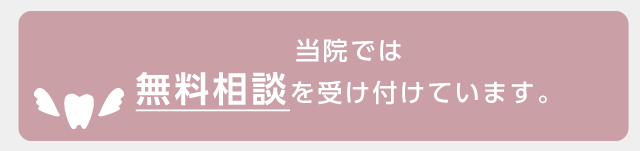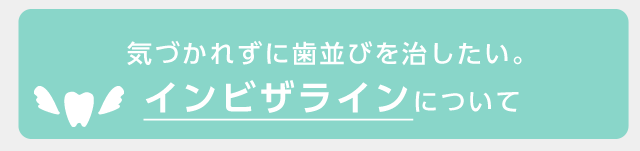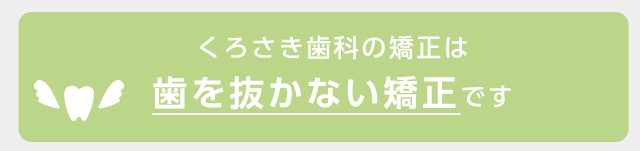歯周病じゃないのに歯が揺れる! 咬合性外傷とはどのような症状?

歯のトラブルの中に「咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)」と呼ばれる症状があります。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、放っておくと全身に悪影響を及ぼしてしまう症状なので、迅速な治療や日々の予防が大切になります。
それでは咬合性外傷とはどういった症状なのでしょうか。今回はこの咬合性外傷について紹介し、原因や予防法、罹ってしまった時の治療法などを紹介していきます。
Contents
咬合性外傷とは

咬合性外傷は「歯にかかる力」によって発生してしまう症状です。
一般的な歯周病は歯に付着した歯垢が原因ですが、咬合性外傷は歯にかかってしまう負担によって発生するケースが多いのが特徴です。
例えば硬い食べ物を食べる習慣がほとんどない状態で、噛み応えのあるものを食べると、歯の土台に当たる部分が損傷してしまうことがあります。
歯と骨をつなぐ部分には「歯根膜」というものがあるのですが、この組織がダメージを受け、線維が切れてしまうことで、骨との接合部が緩んでしまい発症してしまうこともあります。
また咬合性外傷は、就寝時の動作によって引き起こしてしまう可能性があり、眠っている時の習慣によって発症リスクを高めてしまう病気です。眠っている時に歯ぎしりをしてしまったり、歯を食いしばってしまうことが癖になっていたりする場合でも歯槽骨や歯根膜を傷つけてしまうケースもあります。
虫歯や歯周病ではないのに歯が痛くなる、歯がグラグラと揺れる、突然歯が折れる、知覚過敏が出やすくなるなどの症状を発生させてしまうのが咬合性外傷なのです。
一般的な咬合性外傷は、歯垢から出る細菌によって発症するものではないため、厳密にいうと「歯周病」とはいえません。ですが歯のぐらつきや歯周ポケットを作ってしまうことから、そこから細菌が入り込み歯周病を発症させてしまう可能性があります。
他にも歯周ポケットが大きくなることから、歯を構成している成分がポケットから溶け出してしまい、咬合性外傷を悪化させてしまうこともあるため注意が必要です。
咬合性外傷で見られる症状とは

歯に不具合を感じた際に以下の症状に心当たりがある方は、咬合性外傷の可能性があります。
ご自身の口内トラブルと照らし合わせて確認してみてください。
咬合性外傷で頻繁に起きる症状
・歯の違和感(歯が浮いたような感覚)
咬合性外傷では「歯が浮いたような感触」を覚えることがあります。食べ物を噛んだ際に違和感を覚えたら咬合性外傷を発症させてしまっているかもしれません。
その後、違和感が大きくなり、次第に「冷たい食べ物が歯にしみる」「歯が揺れるようになる」という症状になった場合は咬合性外傷を引き起こしている可能性があります。
・起床時に口内がむず痒く感じる
朝起きた際に、歯の周りがむず痒く感じる方は、就寝時に歯に強い負担がかかっている傾向があります。起床後、口内に違和感を覚える日が続くと、次第に歯が浮きだしてしまうことがあるため注意が必要です。
・詰め物や被せ物が突然取れる
片側噛みや歯ぎしりを頻繁に行ってしまう人は、歯が次第にすり減り欠けていくため、虫歯治療などで取り付けてもらった詰め物や被せ物が取れやすい傾向があります。
もし詰め物や被せ物が取れてしまった場合、根本的な原因は咬合性外傷である可能性もあるのです。
咬合性外傷で時々見られる症状
咬合性外傷では、口内とは全く違った箇所で痛みを感じるようになることもあります。
中には口内や顎まわりの痛みを超えて、頭痛や肩こりなどを訴える方もいらっしゃいます。口内の異変の他にも体調不良を感じる場合は、咬合性外傷によって引き起こされている可能性があることを知っておきましょう。
その他にも舌の痛みや眼の奥の痛みなども咬合性外傷と関連があるケースもあります。
歯科医に咬合性外傷について相談する際には、口内のトラブル以外の身体の異変も伝えておいた方が良いでしょう。
歯周病と併発している時の特徴
咬合性外傷は、一次性と二次性のものに分類されます。
一次性咬合性外傷は、健康な歯周組織に支えられた歯に、今回紹介したような歯ぎしりや食いしばりなどの強い咬合力が加わってできる損傷です。その一方で二次性咬合性外傷というものは、すでに歯周病になり、脆くなった歯周組織に支えられた歯に刺激が加わることで起きてしまう損傷を指します。
二次性の場合、通常の歯周組織では全く問題ないような弱い咬合力でも損傷が発生してしまうため、今回紹介した症状がより深刻になる傾向があります。歯の揺れや顎関節にまで支障が出てきてしまい、更には肩こり、首こり、頭痛をより深刻にしてしまうケースも少なくありません。
咬合性外傷が発生する原因とは

咬合性外傷は、歯根膜に強い衝撃が加わって損傷することから発生してしまうものなので、以下のような負担を与えてしまう行為が咬合性外傷を発生させる原因といえます。
歯ぎしり、歯の食いしばり
主に就寝時などに歯ぎしりを行ってしまったり、歯を強く食いしばったりする習慣があると、噛み合わせのバランスが崩れてしまい、一部の歯に強い負担がかかりがちになります。
歯に偏った力が加わってしまうと、次第に歯周組織にダメージが蓄積されてしまうようになり、そこから咬合性外傷を発生させてしまう原因に繋がるのです。
被せものや詰めもの
歯の噛み合わせはデリケートなもので、20〜30ミクロンの違いですら感じ取ってしまうほどとされています。そのため被せ物や詰め物が多くなると噛み合わせに違和感を覚えるようになり、一部の歯に偏った力が加わってしまう可能性があります。
歯並び
歯並びは「見た目」や「歯磨きのしやすさ」だけでなく、噛み合わせにおいても大切なポイントです。
例えば歯が噛み合っておらず奥歯だけで噛んでいる状態になっていると、奥歯の負担が大きくなりがちで、咬合性外傷を発症させるリスクを高めてしまいます。
また歯並びが悪く磨き残しが増えてしまうと、歯周病を発症するリスクも高めてしまうため、治療が難しい二次性咬合性外傷を引き起こしてしまう可能性もあるのです。
咬合性外傷の治療法

咬合性外傷の治療では、主に以下のようなアプローチをかけていきます。
患部の観察と検査
噛み合わせの状態を確認するために歯をチェックします。主に確認することは歯周ポケットがどれだけ深くなっているか、歯がどれだけ揺れているかを調査することと、レントゲンを撮影し歯周組織の状況を調べることです。
ここで歯周病の原因になる歯垢もチェックし、歯周病が併発していないかを確認します。
歯垢の除去(プラークコントロール)
咬合性外傷と歯周病が併発している状態の場合、歯磨きによって歯垢を取り除くプラークコントロールを行います。歯垢を取り除くことができた後に、咬合性外傷の治療を行うのが一般的です。
噛み合わせの調整をする
噛み合わせが悪い方の特徴として「一部の歯に力が入りがち」という傾向があります。
そのため咬合性外傷の治療は、それぞれの歯に対して噛む力が均等になるように調整を行う場合もあります。場合によっては周囲の歯を削り、負荷がかからないような歯並びを形成していき、理想的な噛み合わせを作っていくのです。
歯並びが悪い場合は専門医による歯列矯正治療なども行い、咬合性外傷を悪化させない噛み合わせになるよう治療を続けていきます。
歯ぎしりの治療
咬合性外傷において、歯ぎしりは重要な原因の1つとして考えられており、治療の際には改善が欠かせません。
就寝中の歯ぎしり対策のために歯科医からマウスピースの使用を勧められ、日常生活で取り付けることによって治療を進めていきます。マウスピースを活用することで歯や歯周組織への負担を軽減させ、咬合性外傷の悪化を抑える役割があるのです。
咬合性外傷の予防法

咬合性外傷は日々の生活習慣によって発症のリスクを抑えることができます。咬合性外傷を防ぐための日々の予防法は以下の通りです。
口内環境を整える
咬合性外傷は口内環境が乱れていると発症しやすいという特徴があります。そのため予防の基本として「口内環境を清潔に保つ」というのは欠かせないでしょう。
口腔内が綺麗な状態で保てると、歯周病予防や虫歯予防にもなります。歯周病と併発してしまうと怖い咬合性外傷ですが、口腔内を清潔な状態にしておくことで咬合性外傷、歯周病の両方の発症を抑えることができるのです。特に糖尿病を患っている方は免疫力が低下しており、細菌感染しやすいため、口腔内の環境を整えることは特に大切です。
唾液の分泌を促進させる
唾液の分泌量が少なくなると細菌が繁殖しやすい口内環境になってしまいます。
唾液の分泌はストレスなどの自律神経の乱れによって減ってしまうため、リラックスできる生活環境を構築することも大切です。食事の際には食べ物を十分に噛んでから飲み込むよう心がけ、1口につき30回は噛むように意識しておきましょう。
咬み合わせを整える
噛み合わせに問題があり、一部の歯にだけ力が加わっていたり、逆に全く力が入っていなかったりすると、咬合性外傷を発生させるリスクを高めてしまいます。
噛み合わせに関する不具合は日常生活ではなかなか見つけにくいものなので、定期的に歯科検診を受け、噛み合わせをチェックしてもらうことがおすすめです。
また治療していない虫歯がある状態で過ごしていると、虫歯のない方向で噛む癖がついてしまいがちです。これは咬合性外傷を発生させるリスクを高めてしまうため、なるべく早く虫歯は治療し、左右両方の歯で噛むようにしておきましょう。
マウスピースを活用する
歯並びに問題がなかったとしても、就寝時に無意識に歯ぎしりや歯の食いしばりを行っていると咬合性外傷を発症させるリスクを高めてしまいます。もし自分が就寝時に歯ぎしりをしていることが分かったのなら、マウスピースを装着して就寝することも検討してみましょう。
料金はかかりますが、マウスピースは保険診療で作ることができるため、そこまで高い費用がかかるわけではありません。歯科で自分専用のマウスピースを入手できれば、歯や歯茎にかかる力を抑えることができ、負担を軽減させることができるでしょう。
咬合性外傷のセルフチェック術

自分が咬合性外傷になっているかどうかを確認する際には「歯ぎしり・食いしばりの習慣があるかどうか」を確認することがおすすめです。
これらの癖を確認するためには、以下の項目に該当しているかを見ていきます。これから紹介する内容に該当する方は歯ぎしりや食いしばりをしている可能性が高く、咬合性外傷を発症するリスクが高いと考えられます。
- 起床時に口の周りやこめかみが疲れている感じがする。あるいは痛みを感じることがある。
- 歯や歯茎が痛い(水がしみる)。
- 顎にだるさを感じたり、痛みを感じることがある。
- 何かに集中している時に、ふと気付くと無意識に歯を食いしばっている。
- ここ最近、肩こりや頭痛に悩んでいる。
- 舌に歯の跡がついているのを見たことがある。
- 鏡を見てみると、犬歯の先端がすり減って平らになっている。
ここまでで紹介した内容の中で、心当たりがある項目が複数個ある方は、今後咬合性外傷を発症する可能性があります。
歯ぎしりや食いしばりは無意識で行っているケースが多いため、日常的には気付きにくいものです。ですが上記のように1つ1つ確認してみると「自分も咬合性外傷なのでは……?」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。気になる点がありましたら、まずは歯科医に相談をしてみましょう。

一次性咬合性外傷は細菌からの侵入というわけではないため、偏った噛み合わせの力を分散させることで、時間はかかりますが歯根膜を再生させることは可能です。その一方で二次性咬合性外傷のような細菌が問題となっている場合は歯根膜の修復は難しく、いずれは歯が抜け落ちてしまうケースも少なくありません。咬合性外傷が完治できるかどうかは発症の原因によって違いますが、いずれにせよ発症を未然に防ぐためにも予防を心がけたいものです。
定期的に歯科に通い検査を受け、咬合性外傷を発症させないことを意識しましょう。