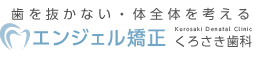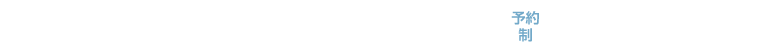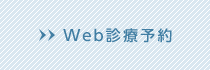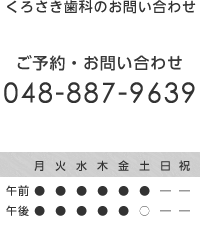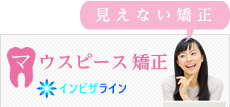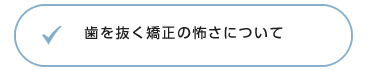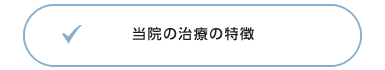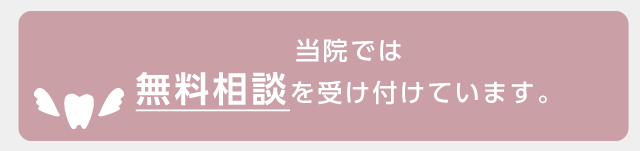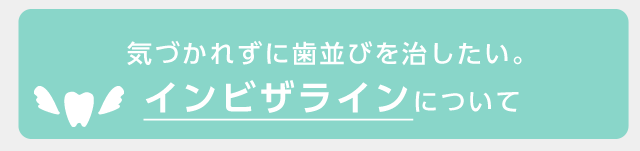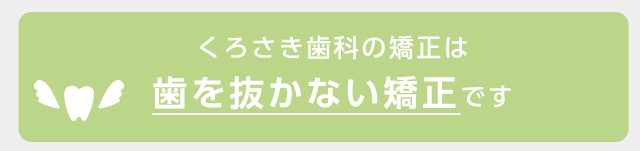酸蝕歯はどうして起こる? 原因と予防法

酸蝕歯(さんしょくし)という病気をご存知でしょうか? 酸蝕歯は読んで字のごとく、酸に蝕まれた歯のことを指します。酸性の強いものを頻繁に食べたり飲んだりすることで、歯の表面のエナメル質が溶けだす病気です。
歯の病気として虫歯というのは有名で、普段から虫歯にならないよう気をつけている方も多いと思います。しかし酸蝕歯は、虫歯ケアをしていても発症してしまうことがあり、特別な予防策を講じることが必要ですので知っておきましょう。
ここでは、虫歯と同じように気をつけておきたい、酸蝕歯の原因や予防法などをご紹介します。

Contents
酸蝕歯とは
酸蝕歯とは、酸性の食べ物や飲み物を多く口にすることにより、歯が溶けてしまう病気のことです。表面が溶けて中の象牙質がむき出しになることで、歯がしみたり形が悪くなってしまったりなどの症状が現れます。
表面をエナメル質で覆われている人間の歯は硬いという特徴を持っていますが、酸に弱いという性質を持っています。普通は、唾液が酸を洗い流して中和してくれるのですが、何度も繰り返し酸性のものを口に入れることで、唾液の中和作用が追いつかず、エナメル質が溶けだしてしまうのです(歯の表面が溶けることを脱灰といい、唾液の中和作用でエナメル質が元に戻ることを再石灰化といいます)。
最初は歯の表面のエナメル質が柔らかくなり、さらに進むと歯の表面が溶けだして中の象牙質がむき出しになってしまいます。象牙質は脆く、神経が走っていることもあり、歯がしみるような不快感や痛みが生じます。この状態が酸蝕歯です。
虫歯は口の中(歯)の一部で発症することが多いですが、酸蝕歯は口の中全体で起こることが多いため、症状の度合いによっては虫歯よりも深刻な病気であるという見方もあります。酸性の強い食事をあまり取らないようにするなど、食生活そのものを見直す必要があるため、虫歯対策をしているだけでは酸蝕歯予防にはなりません。
酸蝕歯を引き起こしやすくしてしまう原因を知り、適切な予防策を練る必要があります。

酸蝕歯の原因
酸蝕歯の原因は、酸性の強い食べ物や飲み物を多く口にすることです。以下のような生活を送る方は、特に酸蝕歯になりやすいといわれていますので、自分が当てはまるかどうかチェックしてみてください。
・炭酸飲料を頻繁に飲む
・水分補給のためにスポーツドリンクを頻繁に飲む
・みかんやレモンなどの柑橘系の果物をよく食べる
・酢の物や梅干しなどを頻繁に食べる
・サラダを食べるときはマヨネーズやドレッシングを必ずかける
・黒酢を頻繁に飲む
・洗口液でうがいをしてから寝る
・寝る前などにワイン、ビール、チューハイを飲んでから寝る
・摂食障害などでたびたび嘔吐する
・果物やアルコール類を飲食した直後、歯ブラシで力強く歯を磨く
酸性かアルカリ性かどうかは、pH値(ペーハー値)によって示され、pH値7が中性です。数値が低ければ低いほど酸性が強いとなり、通常、口の中はpH値が6.5~7という、弱酸性から中性となっています。
エナメル質が溶けだしてしまうpH値は5.5です。つまり、5.5位のpH値の飲食物を頻繁にとると、酸蝕歯になりやすくなります。上記の酸蝕歯になりやすい生活習慣の中に出てくる飲食物は、すべてpH値が5.5を下回っている、酸性の強いものです。以下にpH値の低い飲食物と、そのpH値を紹介しますので、参考にしてみてください。
・レモン:pH3.3~4.0
・炭酸飲料:pH2.6~3.4
・リンゴ:pH3.9~4.5
・黒酢:pH3.3~4.0
・ワイン:pH2.8~3.6
・ビール:pH3.8~4.1
pH5.5がエナメル質を溶かす基準ですから、上記の飲食物がいかに酸蝕歯を引き起こしやすくしてしまうかわかると思います。これらのものを頻繁に口にするという方は、できるだけ控えるなどしたほうがいいかもしれません。
また、酸の種類によっても酸蝕歯を進行させやすいものがあります。例えば、ソフトドリンクに含まれていることが多い酸に、クエン酸とリン酸とがありますが、クエン酸のほうがより酸蝕歯を進行させやすいといわれています。ほかにも、カルシウムキレート(溶けたカルシウムを結合すること)の効果が高い飲料水も、酸蝕歯を進行させやすいといわれていますので、飲料水を飲むときはどのような成分が入っているのか確認してから飲むようにしましょう。

酸蝕歯の症状
酸蝕歯は虫歯と違い、歯に穴が空いたり、常に痛みが発生したりするというようなことはありません。自分では健康だと思っていたのに、調べてみたら酸蝕歯だったというケースも多くあります。
自覚症状がほとんどなく気がついたら進行しているという特徴がある病気ですので、日ごろから自分で意識的にチェックするようにしましょう。以下に酸蝕歯の症状についてご紹介します。
【初期症状】
・光を当てると、歯の先端部分が透けているように見える
・熱い、冷たい飲食物が歯にしみる
・歯の表面にツヤがなくなる
・歯全体が丸みを帯びているように見える
・歯が少し黄ばんでいるように見える
これらの初期症状が進むと、以下のような症状が出てきます。
【中期症状】
・歯の先端部分が透けて見える
・熱い、冷たい飲食物がひどくしみる
・歯の表面に小さな凹凸ができる
・歯がかなり黄ばんでいる
・以前詰めていた歯の詰め物が取れやすくなる
このような症状が見られるようになったら、酸蝕歯がかなり進行している可能性がありますので、かかりつけの歯科医に診てもらうようにしましょう。

酸蝕歯を予防するには
酸蝕歯は、歯の表面が溶けて象牙質がむき出しになってしまう病気ですか、軽度のもの(初期症状の段階)であれば、治療をしなくても実害はありません。初期症状が見え始めたら、生活習慣を変えて、酸蝕歯の進行を止めるように心がけましょう。
【酸蝕歯の予防法】
・酸性の強い飲食物を避ける
酸蝕歯の進行を予防するには、酸性の強いものを極力避けるようにするというのが定石です。しかし、酸性が強いからといって、そのすべてを避けることはできません。食事や飲み物の内容だけではなく、食事の取り方や生活習慣に変えていく必要があります。
・口の中に飲食物が長いこと入っていないようにする
酸性の強い食べ物が口の中に長い間入っている状態が続くと、より酸蝕歯になりやすくなります。だらだらと食べ続けない、間食をしない、食べ物は噛み終わったらすぐに飲み込む、食後には水やお茶を飲むなど、食べ物が口の中に留まり続けないよう気を付けましょう。
・寝る前に食べない
就寝中は口の中の唾液の分泌量が減り、歯の再石灰化が起こりにくくなります。そのため、就寝前に酸性の強いものを口にしてしまうと、夜寝ている間に酸蝕歯が進行しやすくなるのです。就寝前に飲食するという方は、できるだけ控えるようにしましょう。
・食後30分は歯磨きをしない
歯のエナメル質は酸に触れることで柔らかくなってしまいます。そのため、酸性の強いものを口にしたあと、すぐに歯ブラシでゴシゴシと強く歯を磨いてしまうとエナメル質が削られてしまい、酸蝕歯になりやすくなるので、歯を磨くときは食後にすぐ行わない、強く磨きすぎない、などに気をつける必要があります。
・フッ素、リカルデントの入った歯磨き粉を使う
酸蝕歯の進行をストップさせるためには、歯の再石灰化を促すことが必要です。フッ素やリカルデントには、歯を硬くする作用や、歯の再石灰化を促す作用があります。フッ素やリカルデントを含んだ歯磨き粉や、ジェル、ガムなどがありますので、それらを選んで使用するようにしましょう。
・ガムを噛んで唾液の分泌を促す
酸蝕歯予防には、唾液の分泌を増やすことが効果的です。ガムを噛むと、自然と唾液の分泌量が増えてくれます。しかし、糖分の入ったものだと虫歯につながってしまう可能性がありますので、糖分の入っていない、歯科専用のガムを噛むようにしてください。その際は前述のフッ素やリカルデントの含まれたガムを選ぶと、より酸蝕歯予防になります。

以上のことを行うことで酸蝕歯の進行を防ぎやすくなります。しかし、これらはあくまで予防法ですので、酸蝕歯の進行が止まっているのか不安だという方は、かかりつけの歯科医を受診するようにしてください。

歯科医で行う酸蝕歯の治療法
酸蝕歯が進行している場合(中期症状が見られる場合)は、歯科医で治療を受ける必要があります。エナメル質が溶けだして、象牙質が露出している可能性が考えられるからです。そのような状態になってしまうと、生活習慣を変えただけでは改善しにくくなるからです。
歯科医で行われる酸蝕歯治療は、症状の度合いによってさまざまな方法が取られますが、一般的には以下のような治療が行われます。
・コンポジットレジン充填
酸蝕歯の中期症状である、歯に凹凸ができるという症状が見られる場合は、凹んでいる部分を詰め物で埋める治療を行います。コンポジットレジンは虫歯治療で用いられる白い詰め物で、虫歯治療と同じように、酸蝕歯によって欠損した歯の一部に詰めます。
・フルクラウン治療
歯の欠損部分(凹み)が大きい場合、詰め物ではなく被せ物を使う治療を行います。神経まで達した虫歯を治療するときと同様、ケースによっては歯の神経を抜き、クラウンという被せ物で歯を覆います。
・ラミネートべニア治療
酸蝕歯が進行し、歯が黄ばんだり、形が悪くなってしまったりするときに行う治療です。歯の表面を0.5ミリ程度削り、そこに白い板を張り付けます。見た目をよくするための治療ですので、自費治療となることが多いですが、酸蝕歯によって黄ばんでしまった前歯が気になる、という方におすすめの治療法です。

酸蝕歯は虫歯と違って、自覚症状があまりない病気です。気がついたときにはかなり進行しているということが多いので、日ごろから自分の歯の様子を意識的に確認するようにして、適切な対処ができるようにしておきましょう。
ここで紹介した予防法である程度酸蝕歯の進行を抑えることができますが、それでも症状が改善されない場合は、早めに歯科医に診てもらい、適切な処置を取ってもらうようにしてください。