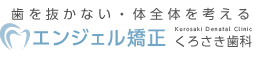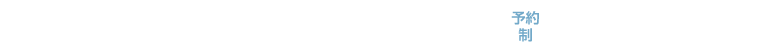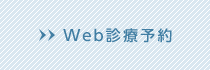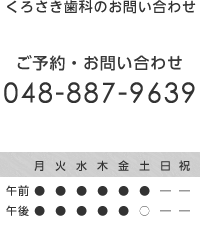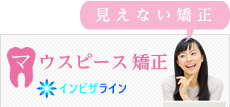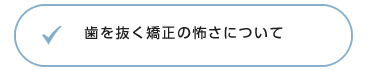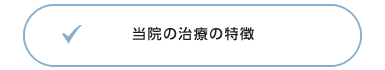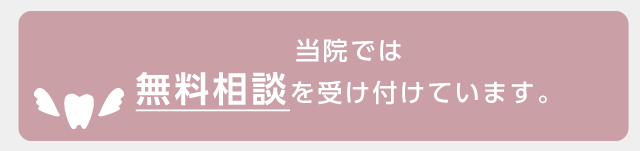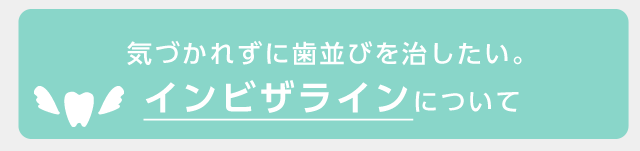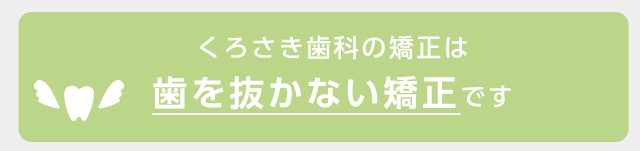【虫歯予防の大切さ】いつまでも健康でキレイな歯で過ごすには

永久歯は15歳前後で生えそろって以降、一生を共にするものです。きちんとケアを続けていれば虫歯などの病気にかかることなく、一生涯自分の歯で過ごすこともできるもの。いつまでも健康でキレイな歯を保つには、どのような工夫を続けていけば良いのでしょうか。
今回は虫歯予防で大切なことをご紹介します。虫歯の進行や歯の再生能力のメカニズムについて解説し、日常生活の中で続けられる虫歯予防習慣についてご説明していきます。
Contents
虫歯予防で知っておきたい「脱灰」と「再石灰化」

人間の歯は、日常的に「脱灰」と「再石灰化」という2つの現象を繰り返しています。
「脱灰」とは、歯の表面からカルシウムイオンやリン酸イオンといったミネラル分が溶けだした状態を指す言葉。脱灰が進むと歯のエナメル質の光沢が薄れ、乳白色に濁った部分ができます。
一方「再石灰化」については、テレビCMなどでこの言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。再石灰化は、脱灰によって失われたミネラル分が唾液などの働きで補われ、再び歯の表面を覆うエナメル質として再形成される現象です。
歯の表面や根元にプラーク(歯垢)や食べかすが残った状態では、その中で虫歯菌(ミュータンス菌)が繁殖してしまいます。虫歯菌は糖分を食べることで酸を放出するため、食事の後は口腔内のpH値が低下して酸性に傾きます。
その結果、歯のエナメル質の9割を構成するハイドロキシアパタイト(リン酸カルシウムの結晶)が溶かされ、カルシウムイオンやリン酸イオンといったミネラル分として流れ出てしてしまうのです。
虫歯菌が歯を溶かす作用は「う蝕」と呼ばれており、脱灰状態は虫歯の中で最初期の進行度C0にあたります。一般にイメージされる穴が空いた状態の虫歯は、脱灰によって生まれた小さなほころびから作られてしまうのです。以前は脱灰した部分も虫歯として削り取っていたのですが、最近では大掛かりな治療は行わず、再石灰化を促す治療のみでケアしていくことが一般化しています。
ただ、人間の歯や口腔内には再生能力が備わっており、食事を終えてしばらくすると、唾液の働きによって口腔内のpH値は少しずつ上昇していきます。すると歯の失われたカルシウムイオンやリン酸イオンが補われていき、再びエナメル質が再形成されていく仕組みになっているのです。
虫歯予防に役立つ2つの成分
歯のエナメル質を強くする「フッ素(フッ化カルシウム)」

フッ素を含む食べ物は、“歯を強くする”食品として紹介されることも多いです。
再石灰化によってハイドロキシアパタイトが再形成されるとき、フッ素を取り込むことでフルオロアパタイトという成分に変化します。「フッ素リン灰石」とも呼ばれるフルオロアパタイトは高い耐酸性を持ち、エナメル質を脱灰しづらい状態にしてくれます。
脱灰が進んだ最初期の虫歯程度なら、フッ素を塗布する治療で治せるケースも少なくありません。再石灰化のときにフッ素が介入すると、通常時より多くのフッ素を取り込むことができるため、エナメル質の再生がスムーズに行われるようになるのです。
また、フッ素は虫歯菌の活動を抑える働きも持ち合わせています。フッ素が虫歯菌の酸の放出自体を抑えてくれるため、歯が溶かされづらい状態、つまり虫歯が進行しづらい口腔内環境に近づけてくれるのです。
フッ素は、歯をより丈夫で虫歯になりにくい状態にしてくれる成分といえます。もちろんフッ素だけあれば虫歯にはならないという訳ではありませんが、虫歯予防の強い味方になってくることは間違いないでしょう。
虫歯菌の活動を抑える「キシリトール」

虫歯予防に一役買ってくれる成分としては、人工甘味料であるキシリトールも有名です。
キシリトールは白樺やトウモロコシの芯部分から精製される成分で、砂糖と同じくらいの甘味を持つ天然由来の甘味料。大きな特徴としては、その成分が虫歯菌のエサにならないという点が挙げられます。
虫歯菌は、ブドウ糖や果糖に由来する糖分などをエサにして酸を放出しますが、キシリトールからはほとんどエネルギーを取り出すことができません。キシリトールは糖の一種なので一度は虫歯菌に食べられてしまうのですが、酸を放出するためのエネルギーを取り出すことができず、そのまま排出されてしまいます。途中までは消化できるのにエネルギーには変換できないため、虫歯菌はどんどん消耗していってしまいます。
このような「無益回路」を介した代謝阻害により、キシリトールは虫歯菌の活動を抑えてくれるのです。日本フィンランドむし歯防止研究会によれば「キシリトールは口の中で「酸」をまったく作りません」との見解が示されています。
キシリトールは直接虫歯菌を減らしたり、再石灰化を引き起こしたりするわけではありませんが、間接的に口腔内を再石灰化しやすい状態にしてくれる成分なのです。
毎日の食生活に取り入れたい“歯に良い”食べ物
フッ素やキシリトールを含む食べ物、歯のコンディションを整えてくれる食べ物など、“歯に良い”食品を積極的に取り入れていきましょう。
チーズや牛乳など乳製品

カルシウムやフッ素を含む乳製品は、初期の虫歯(脱灰状態)のケアに適した食材です。
チーズや牛乳などの食品にはリン酸カルシウムが多く含まれているため、口腔内のpH値をアルカリ性に近づけてくれます。牛乳は毎日の食事に取り入れやすいですし、チェダーチーズなどの固いものを噛めば唾液の分泌も促されます。
ただしヨーグルトなどに多くふくまれる乳酸菌「ラクトバシラス」は、すでに虫歯が進行して穴が空いた状態では、さらに虫歯を悪化させてしまうことがあるので注意しましょう。
ビタミンDを含む魚やキノコ類
骨や歯を強くするためにはカルシウムだけでなく、その吸収を助けるビタミンDの摂取も必要です。魚やキノコ類といった食べ物にはビタミンDが豊富に含まれています。特に天日干しの干し椎茸はビタミンDが豊富だといわれており、料理への使い勝手も良いので、積極的に食事へ取り入れたい食材です。
ビタミンDは食べ物から吸収するだけでなく、日光(紫外線)を浴びて体内で合成することもできる成分です。ビタミンD摂取以外に、運動や日光浴など基本的な生活習慣にも目を向けてみてください。
粘膜の調子を整える柑橘系の果物
オレンジやミカンといった柑橘系の果物には、歯茎を強くしてくれるビタミンCが豊富に含まれています。肌のコンディションを整えてくれることで知られるビタミン群ですが、歯茎に対してはコラーゲン繊維の再生を手助けしてくれるため、歯肉炎予防に繋がる成分として貢献してくれるのです。歯茎のコンディションが良くなり、プラークが溜まりづらい口腔内環境になれば虫歯になるリスクも低減します。
ただ、酸味の強いシトラス系の果物はエナメル質を柔らかくしてしまうことがあります。酸っぱいフルーツを食べるときは1日1個程度の分量に留め、食べ過ぎに注意してください。
フッ素を多く含むイチゴやサクランボ

イチゴやサクランボといったフルーツは、歯を強くするために必要な成分 フッ素が多く含まれた果物です。歯科クリニックで行っているフッ素材ほどの量ではありませんが、日常生活で手に入る食材の中ではフッ素を豊富に含んでいます。食べやすい大きさでついつい摘まんでしまうサイズ感なので、食後のデザートにもピッタリの食品。ただし、どちらも糖分を多く含む果物なので、歯磨きなどは忘れずに行いましょう。
エナメル質形成にも大切な緑黄色野菜
歯のエナメル質のコンディションを整えるために、ビタミンAが豊富な食品を積極的に取り入れましょう。ほうれん草やニンジン、バジルといった緑黄色野菜にはビタミンAが多く含まれており、毎日の食生活に取り入れやすい食材といえます。
ビタミンAは、エナメル質の土台となる歯胚形成期に大切な成分で、歯の成長・修復をスムーズに進めるために不可欠な栄養素です。他のビタミン群と同じように肌や粘膜のコンディションを整えることにも役立つ他、抗酸化作用により口腔内のpH値を上げ、虫歯菌などの細菌の活動を抑えるためにも一役買ってくれる頼もしい成分なのです。
ビタミンAはチーズや卵、うなぎなどにも含まれているため、さまざまな食材を偏りなく食事に取り入れていってください。
虫歯を予防するために大切な生活習慣
食後は早めに歯磨きをする

食事を済ませた後は、できるだけ早めに歯磨きをするようにしましょう。早めに食べかすやプラークを除去して、虫歯菌が活動する時間を与えないことが虫歯予防にとって大切です。
ポイントは、優しく丁寧にブラッシングすること。食後の口腔内は酸性の状態になっているため、歯のエナメル質も比較的脆い状態にあります。この状態で乱暴にブラッシングをしてしまうと、エナメル質に傷をつけてしまう可能性が高いのです。できるだけ早めに歯を磨くことは重要ですが、優しくブラッシングするよう心がけてください。
歯磨き粉の選び方も重要
歯磨き粉の選び方についてもポイントを確認しておきましょう。
虫歯に強い歯を手に入れるためには、フッ素配合の歯磨き粉がおすすめです。歯磨き粉に含まれているフッ素は歯科クリニックのフッ素材ほどの濃度ではありません。しかしながら少量でも繰り返しフッ素を塗布していくことで、歯を虫歯に負けないコンディションに近づけていくことができます。
また、エナメル質を傷つけないために研磨剤が少ないものを選ぶことも大切です。歯の着色汚れを除去する「ホワイトニング」「ステイン除去」系の歯磨き粉には、研磨剤が多く含まれているものが見受けられます。虫歯予防の観点からいえば、低研磨剤の歯磨き粉を選ぶようにしましょう。
デンタルフロス・歯間ブラシを使う

大手オーラルケア製品メーカーによれば、歯磨き(ブラッシング)のみで除去できるプラークの割合は6割程度だといわれています。歯の表面や歯周ポケットだけでなく、歯の間に溜まったプラークも定期的に除去すべきです。数日から1週間に1度程度でも良いので、デンタルフロスや歯間ブラシなどで歯間のプラークも取り除く習慣をつけましょう。
普段のブラッシングに糸状のデンタルフロスか、樹脂などでできた歯間ブラシを併用すると、プラーク除去率は8割程度まで向上するそうです。できれば歯ブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロス全てを併用するのが理想的。普段は歯ブラシでこまめに歯磨きを続け、週末など時間のあるときはフロスや歯間ブラシで集中ケアする、といった習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。
間食はできるだけ減らす
食べ物を口にする回数が増えると、口腔内が酸性に傾いている時間が長くなってしまい、虫歯菌の働きを助けることになってしまいます。
食事の後、唾液が口腔内の酸を洗い流してpH値を中性に近づけるためには、おおむね1時間程度かかるといわれています。間食が多かったり、食べ物を口に含んでいる時間が長くなったりしてしまうと、その分口腔内が酸性である時間も長くなってしまうのです。食事と食事の間には、最低でも2,3時間間隔を空けると良いでしょう。
虫歯予防は、食事やデンタルケアなど毎日の積み重ねが大切です。食事や歯磨きのポイントなど、今回ご紹介した内容をぜひ日々の生活習慣に取り入れてみてください。
また歯の状態を正確にチェックすることや、歯に固着した歯石を取り除くのは、個人ではなかなか難しいといえます。2か月に1度くらいのペースでも、定期的に歯科検診を受けるようにしましょう。