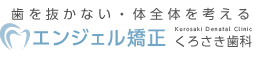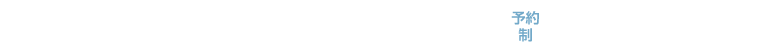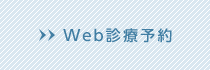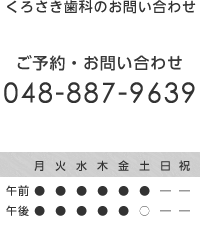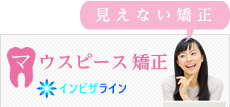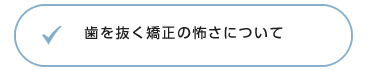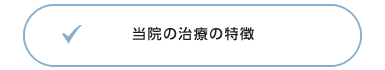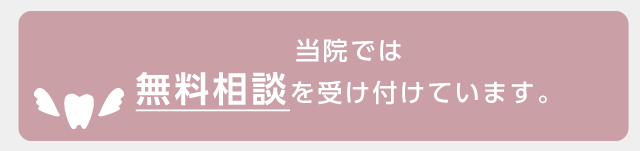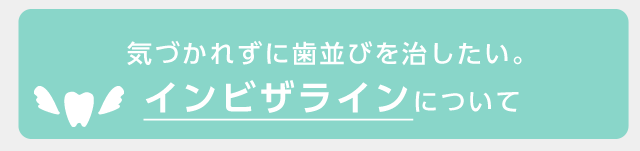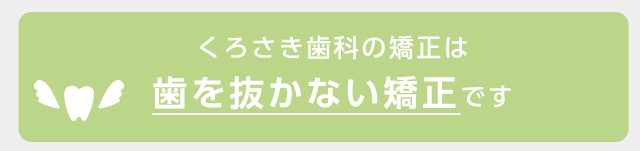歯周病が認知機能を低下させる? 脳の認知機能と歯の関係

年をとっても自分の歯で食事をしたいと考える方は多いと思います。いつまでも健康な歯が生えそろっているのは自信にもなるでしょう。
歯が生えそろっているというのは、見た目や咀嚼機能の点でも利点が多いものですが、最近の研究で残歯数が脳の働きと密接関係にあることが明らかになり、認知機能にも影響があるものであることがわかりました。
今回は歯と脳の認知機能の密接な関係性についてご紹介します。
Contents
歯と脳の関係

歯と脳は一見関係のないものであると思うかもしれませんが、実際は密接な関わりのあるものであることがわかっています。
歯を使ってものを噛むという行為は脳に刺激を与え、感覚や運動、記憶や思考、そして意欲などを司っている部位を活性化するからです。
当然、歯が少なくなり噛むという行為をしなくなってしまうと、咀嚼による脳への刺激が小さくなります。
その結果、脳の活性化が促されず、脳の機能そのものが低下してしまうのです。
また、広島大学がマウスを使い行った実験では、歯の少ないマウスはアルツハイマー型認知症の原因になると言われているアミロイドβタンパクが大脳皮質に沈殿しやすくなったという結果が出ています。
歯と脳の認知機能が密接関係にあることは、マウスを使った実験以外(人間を対象にして行った研究)でも明らかになっています。
愛知県に住む65歳以上の男女4千人を4年間追跡して行った研究で、残歯数が20本以上の人と、歯がない(入れ歯やインプラントなどの義歯もつけていない)人とでは認知症の発症率に大きな差があることが
明らかになりました。
その研究では、歯のない人の方が1.9倍も認知症になるリスクが高いという結果になったのです。
ほかにも、「Journal of the American Geriatrics Society」に掲載された九州大学の研究(60歳以上の日本人の男女1566人を5年間追跡し、
残歯数と認知症の発症率を調べた研究)でも、歯の残り本数が20本以下の人のほうが認知症を発症するリスクが増加しているという結果になりました(10~19本のグループで62%、1~9本のグループで81%、歯がないグループで63%ほど、認知症になるリスクが増加している結果になりました)。
歯の残り本数と認知症の直接的な因果関係はまだ医学的に証明はされていませんが、脳の認知機能に影響を与えるものである、また認知症のリスクを高める可能性があるものであることは確かだと言えそうです。
歯と脳が密接関係にあると言われる理由

咀嚼が脳に刺激を与え脳の各部位を活性化するということ以外にも、歯の残りの本数と脳の認知機能が密接な関係にあると言われている理由がいくつかあります。
実際、歯が抜け落ちて入れ歯などの義歯を入れていても、脳の機能は低下すると言われています。
天然歯は神経や歯根膜によって顎とつながっていますが、義歯は顎骨と神経のつながりがないため、歯を通して脳へ入力される刺激や情報の量が少ないからです。
また、自分の歯がないことで特定の食品(例えば硬い食べ物など)を食べられず、食事の楽しみが減ったり栄養バランスが崩れてしまったりといったことも、脳の認知機能に影響を及ぼしていると考えられています。
自分の歯が抜けることで脳の認知機能に何かしらの影響を与えるということになりますが、歯が抜けるという変化自体だけではなく、「歯が抜ける原因」そのものが脳に影響を与えているという考えもあります。
歯が抜ける大きな原因のひとつが歯周病です。歯周病は口腔内に細菌などがたまることで発症しますが、その細菌が脳にも悪影響を及ぼしていると考えられています。
細菌が口腔内から三叉神経や血管を通って脳に達したり、脳以外の場所に広がることで起こる全身性の炎症などが脳に影響を与えたりすることで、認知機能が低下してしまうと言われているのです。
また歯周病は脳卒中のリスクを高めることでも知られていますが、脳卒中は認知症を引き起こす要因のひとつ。
このことから、結果論とは言え歯周病が認知症の要因を作っていると考えられているのです。
歯がなくなることで脳の認知機能を低下させるというよりも、歯がなくなる原因が、認知機能低下の原因にもなっていると考えたほうが正しいかもしれません。
つまり、いつまでもしっかりとした認知機能を持って生活したいのであれば、歯周病予防をして、「健康的な歯」を保ち続ける必要があるということです。
歯が抜け、脳の認知機能にも影響を与える歯周病とは

歯周病は歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に汚れ(プラーク)がたまることで歯茎が腫れ、歯と歯茎の隙間が深くなって、結果的には歯が抜けてしまうという病気です。
歯周病は段階的に進行します。はじめのうちは歯肉炎と呼ばれ、歯周ポケットが2~5㎜ほどの深さになります(健康な歯では2㎜以下)。進行するにつれて歯周ポケットが深くなり、深さが4㎜~6㎜以上ほどに。
その段階になると歯周炎と呼ばれるようになり、歯が揺れるなどの大きな変化が現れるようになります。
歯周病は初期症状がほとんどなく、気が付いて歯科医に診てもらったときにはかなり進行しているということもあります。
歯肉炎の段階でも多少の違和感は生まれるものですので、少しでも変な感じを覚えたら、すぐにお近くの歯科医の診察を受けるようにしてください。
歯周病は年齢とともに罹患率が増えていくと言われており、40歳以上の8割が歯周病患者であると言われています。
前項で紹介した通り、歯周病は脳の認知機能に影響を与えることが指摘されています。
脳の認知機能低下以外にも、脳梗塞や心筋梗塞など直接的に命に係わるもの、妊婦であれば早産や低体重児出産、全身疾患として糖尿病やメタボリックシンドローム、骨粗しょう症やガンといったたくさんの病気の
原因になるとされていますので、40歳以上の方は特に歯周ケアをしっかり行うようにしましょう。

周病予防をしてしっかりした認知機能を維持しよう

健康な歯を保ち、しっかりとした認知機能を維持するには、日ごろからの歯周病ケアが重要です。
また、少しでも歯に違和感があればすぐに歯科医の診察を受けることが必要です。
以下に歯周病の初期段階で現れる症状の例を紹介しておきますので参考にしてみてください。
・歯茎が赤くなる
歯周病になると、特に刺激を与えたわけでもないのに、歯茎が赤くなっていることが多くなります(健康な歯茎はピンク色をしています)。
・歯茎から血が出る
歯茎が赤くなるのと同じで、歯周病になると特に大きな刺激を与えなくても出血してしまうケースがあります(歯磨き程度の刺激で出血するようだったら要注意です)。
・歯が伸びたように見える
歯周病になると歯周ポケットが深くなると同時に、歯茎が痩せて下がり始めます。
やけに歯が伸びたと感じる場合は、歯が伸びたのではなく歯茎が下がっていると考えられ、歯周病になっている可能性が高いです。
・食べ物や飲み物が歯に染みる
歯茎が痩せて下がることで歯がむき出しになり、そこに食べ物が当たることで歯がしみることがあります。
冷たいものを食べたり飲んだりすると顕著になります。
・硬い物を噛むと歯が痛む
歯周病になると歯が浮いてくることがあります。
そのような歯で硬い物を噛むことで、神経に触れて痛みを感じることがあります。
・口臭が強くなったり、膿が出たりする
歯周病が進行すると歯茎全体に影響を及ぼし、歯茎から膿が出てきます。
その膿が原因で口臭が強くなることがあります。
前項で紹介した通り、40歳以上の8割の方が歯周病に罹患していると言われています。
40歳以上の方は定期的、最低でも3か月に1度の頻度で歯科医に通うのが望ましいです。
とはいえ、歯周病は当然40歳未満の方でも発症しうるものですので、誰であれ歯周病ケアは日ごろから行う必要があります。
日ごろから行える歯周病ケアは、日々の歯磨きや歯間ブラシの使用、禁煙などがありますが、それだけでは十分とは言えません。
摂取する栄養バランスについても考慮することが大切です。摂取する栄養が時に、歯周病菌の繁殖を促進してしまうことがあるからです。
歯周病を発症しやすくし、また進行を促す原因になると考えられているのが糖質。
糖質は口腔内を酸性の状態にし、虫歯の原因になることは有名ですが、歯周病とも深い関わりを持っており、糖質を多く摂り過ぎることで歯周病を発症させたり、進行を早めたりします。
というのは、糖質が歯周病の原因になる細菌にとってエサになるのです。
糖質は炭水化物に多く含まれています(炭水化物は食物繊維と糖質で構成されています)。
白米やパン、麺類、当然ケーキやお菓子などをたくさん食べると、細菌のエサが豊富な環境を生み出してしまうことになるため、歯周病が発症、もしくは進行してしまう可能性があるのです。

食後の歯磨きは当然必要になりますが、糖質の量を減らしてみるというのも歯周病予防法のひとつになります。
また、糖質制限はダイエットにもなりますし、歯周病を誘発すると言われている生活習慣病である糖尿病予防にもなります(高血糖になることで体の防御能力が低下し、感染症が起こりやすくなるためです)。
ほかの栄養素をしっかり摂るなど栄養バランスに気をつけ、糖質制限を食生活に導入してみてはいかがでしょうか。

歯が抜けた後の咀嚼能力が脳の認知機能に影響を与えるだけではなく、歯が抜ける原因になる歯周病そのものが脳に直接害を与えるなど、歯と脳の関係は切っても切れない密接なものです。
歯を大切にするというのは、将来の食生活のみならず、日常生活を送る上でも必要な脳を大切にするということにつながります。
厚生労働省や日本歯科医師会が推進している「8020運動(ハチマルニイマルうんどう)」が目指す、「80歳になっても20本以上の自分の歯を保とう」が実現できるように、
日ごろから歯のケアをおこなうようにしておきましょう。