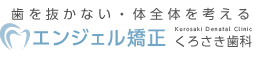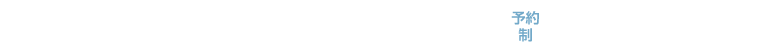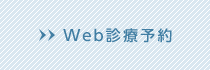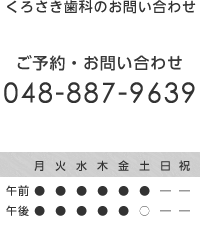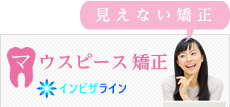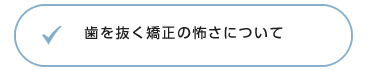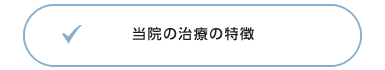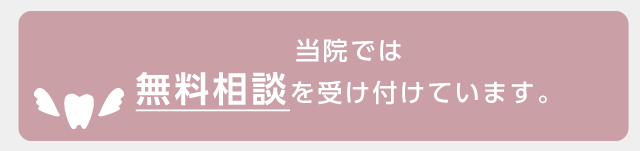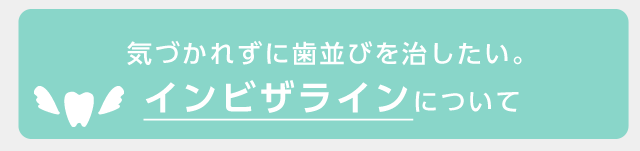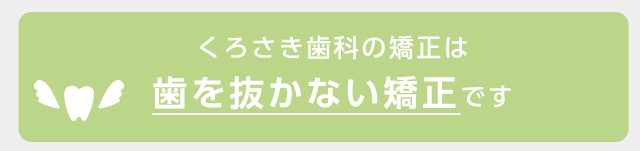口呼吸は歯並びに影響が出るってほんと? 口呼吸をやめる方法は?

季節の変わり目は風邪や花粉症に悩まされて、鼻で呼吸するのが大変なときもありますよね。
口呼吸の癖がつくと、歯並びや顎の形に影響を与えてしまうことがあるのです。
今回は口呼吸の原因と、歯並びや顎に与える影響についてご紹介します。
口呼吸をやめるための対策法も確認しておきましょう。
Contents
口呼吸が癖になってしてしまう原因とは?
口呼吸の癖は、風邪やアレルギー性鼻炎がきっかけで起こることが多いです。
まれに口輪筋や頬筋が弱く自然に口が空いてしまうケースもありますが、大人がなることはあまりありません。
風邪で鼻づまりがひどかったり、扁桃腺が腫れて気道が狭くなると、口で息をして酸素を取り込もうとします。
ですが口呼吸には、鼻のようなフィルターとなる鼻線毛がありません。
そのため菌やウイルスが侵入しやすく、さらに風邪やアレルギーを患って、口で息をするのが常態化してしまう、という悪循環になってしまいます。
風邪などを引いた時だけであれば大きな問題ではありませんが、口呼吸が癖になると噛み合わせや歯並び、さらに顎の形が変わってしまう可能性もあるのです。
口呼吸が歯並びに影響を与える理由

●口呼吸が「低位舌」を招くことがある
口呼吸が癖になると「低位舌」の状態が続き、歯並びなどに影響を与えてしまうかもしれません。
「低位舌」とは、舌が口蓋(口内の上の部分)から離れる状態のことです。
通常、口を閉じているときの舌は口蓋にくっついており、歯を裏側から支えています。
口呼吸の癖がつくと、息をたくさん吸うために「低位舌」になります。
すると内側からの支えが無くなってしまい、口の周りの筋肉による外側からの力とのバランスが崩れてしまうのです。
このように口呼吸による「低位舌」が長い時間続くと、歯列や顎の骨が変形してしまうことがあります。
●歯や顎が変形する「不正咬合」になることも
低位舌が続くと噛み合わせが悪くなったり、顎や輪郭が変形する「不正咬合」になる可能性もあります。
舌や歯を使った発音が悪かったり、食べ物を飲み込みづらくなる場合、不正咬合が原因かもしれません。
さらに症状が進むと、下顎が後退して前歯が突出する「上顎前突」、いわゆる出っ歯になったり、逆に下顎が突出する「反対咬合」になることがあります。
歯並びに悪影響のある口呼吸をやめるには
口呼吸をしてしまう癖は、毎日の習慣で改善することができます。
口呼吸の原因が風邪や花粉症であれば、マスクや専用薬で予防することが大切です。
部屋をこまめに掃除して、ウイルスやアレルゲンの少ない環境を作ることも意識しましょう。
慢性的なアレルギー性鼻炎の方は、歯垢の除去で症状が和らぐ場合があります。
歯垢は菌やウイルスの住み家です。
その細菌が鼻腔を通って、鼻づまりや扁桃腺の腫れといったアレルギー反応を引き起こしている場合があります。
口呼吸が癖になると歯並びが悪くなったり、口臭がひどくなってしまうこともあります。
歯がきれいだと好印象ですし、人と会う時には口臭ケアも大切です。
第一印象をよくするためにも、鼻呼吸の癖をつけてみてはいかがでしょうか?